Foresight
Jan. 14, 2020

大企業の正社員が抱える閉塞感、その正体は
長期観察で人材を評価する日本企業の独自性
[小熊英二] 社会学者、慶應義塾大学総合政策学部 教授
「能力」によって全社員を査定し、「資格」を付与する職能資格制度は、日本企業の1つの特徴といえます。個人の専門性や成績よりも、学歴や就労年数の反映でもある職能=社内のランクで従業員を評価するという仕組みです。これがなぜ連綿と続いているのかというと、企業を横断するような評価基準がないからなんですね。
例えば技能資格があれば、どこの企業に行っても熟練工としての賃金がもらえますし、あるいはMBAを取得していればどこの企業に行ってもそれなりの仕事に就くことができて、それなりの賃金がもらえます。そういうシステムの社会には、自分の能力を証明する横断的な評価基準があるわけです。
EUでは、国を超えて共有できる学位や職業資格の基準を作っています。転職の場合でも新卒の就職の場合でも、その基準に則った資格を提示することで、国を越えて相応の職を得ることができます。
出身校の偏差値や知名度を重視する“学歴”信仰
ところが日本の場合にはそういう企業横断的な基準がないので、結果として、企業は従業員を長期観察して評価するしか方法がない。3年、5年、あるいは10年、どんな働き方をするか、真面目に仕事をするかといったことを上司が観察することによって社内ランクを上げていく。そのやり方が幅を利かせているわけです。
従業員を長期観察して評価するというのは、本当は規模の小さい企業のマネジメント法なんです。でも、事業規模が大きくなっても日本ではこれを実践しているわけですよ。結果として、職務上の専門能力があまり重視されない、人事異動でもって職務があれこれ変わる、卒業した大学が重視されるといったことが起きることになります。
出身大学が露骨に問われるのが新卒者の採用ですね。どこの大学を卒業したかということで、大学入試までの間、地道に努力した人間かどうかということを推し量るわけです。
もともと新卒採用自体、教師による長期観察でお墨付きをもらった学生を「推薦」という形で企業に送り込むことを目的に始まったシステムですから、学校に対する企業の信任は厚い。それが現在も尾を引いて、学位や専門能力でなく偏差値や学校名を重視するという、いわばカギカッコつきの“学歴”信仰につながっているのだと思います。

「慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス 小熊英二研究会」のウェブサイト。
https://oguma.sfc.keio.ac.jp/
成果主義が浸透しないのは、成果を測る指標がないから
一時期、日本企業で成果主義がもてはやされましたけど、結局のところ成果が評価されないまま従来の雇用や人事の慣行を引きずっています。これも、企業を超えて通用する横断的基準や職務区分がなく、一社内での「働きぶり」しか指標がないからです。
成果主義を導入するといっても、実質的にやれたことは非常に短期間の営業成績の評価でしかなかった。あるいは、出来高払いという単純なやり方もありますが、これは単純労働者には適用しやすいけれども、マネジャーのような上級の社員に当てはめるのは難しい。マネジャーは自らの責任と裁量で、一定の予算とメンバーでこれくらいの業務目的を達成せよと部下に対して指示する、いわば目標管理制度が適用されることが多いからです。
マネジメントというのは、本来は組織の目標をマネジャーが決定し、マネジャーが機械のパーツのように肉体労働者や技術者、事務労働者などの配置を行うものなんです。でも日本の課長や部長は、一人で組織の目標を決められる立場にもなければ、部下の採用や配置を決められるわけでもない。つまりマネジャーではなく、部下と一緒に汗を流しながら働く「班長」のようなものです。成果を測る指標がそもそも設定しにくいわけで、だからこそ成果主義が浸透せず、評価の透明化に至らないということなんだと思います。
結局のところ、企業が人材の能力を把握するための方法としては、長期観察という手段しか持ち得ていない。となると、労働者は長期間同じ会社にいないと評価されないということなんですが、全ての社員の給与を年齢ともに上げていくわけにはいきません。人事コストを無尽蔵に膨らませるわけにいきませんから。そこで一部の社員を周縁に排除していかないといけないことになり、出向・女性・高齢者といった立場の人に対する社内の格差を生んでいるのだと思います。

小熊氏の著書『日本社会のしくみ――雇用・教育・福祉の歴史社会学』(講談社現代新書)。日本の働き方がどのように成立してきたかを、データを元にひも解いている。

「大企業型」に分類される人たちも、
その全てが年収が高いわけではない
前編でも説明したとおり、著書『日本社会のしくみ』では、働き手のあり方を大きく3つの類型に分けています。正社員・終身雇用の人生を過ごし、ソーシャルキャピタルの基盤を「カイシャ(職域)」に置く「大企業型」、農業や自営業、地方公務員、建設業など、地域に根付いた職業に就いて「ムラ(地域)」と強くつながる「地元型」、そして会社にも地域にも足場を持たない「残余型」です。
正社員として終身雇用されるというと、地元型や残余型からすると大企業型がうらやましく見えるかもしれませんが、大企業の正社員も、それはそれで閉塞感や息苦しさがあるという声を聞きます。これはなぜなのか。
大企業型は地域とのつながりを養いにくい
1つはそもそも大企業型に分類される人たちも、その全てが決して年収が高いわけではないということが挙げられます。
1990年代以降、日本でシェアが拡大しているのは上位10パーセントの所得者、特にその下半分だとされています*。これは上位1パーセントと、それ以外の99パーセントの格差が大きいアメリカとは違うところです。2012年の調査では、所得上位5パーセントから10パーセントとは年収750万円から580万円に当たります**。2015年の調査でも、給与所得者のうち年間給与が600万円を上回るのは18パーセントで、男性の給与所得者の28パーセントとされています***。
つまり、ほぼ580万か600万ぐらいが、上位10パーセントの所得者の下限と考えられる。ただ年収600万円でも、大都市の世帯で子ども2人が大学に進学すると、可処分所得では生活保護の基準を下回る可能性が出てきます****。ですから、大企業型とそれ以外の格差が開いているものの、大企業型といえども、それほど豊かな暮らしができるとも限らないわけです。当事者の実感としては恐らく、そんなに楽ではないと思いますよ。
そういう経済的な余裕のなさに加え、もう1つ、大企業型はソーシャルキャピタルが職域を通したものに限定されがちで、地域とのつながりを養いにくいことも挙げられるでしょう。そうなると、「この会社を辞めることになったら後がない」「しんどくてもこの会社にしがみつくしかない」という切迫感や悲壮感につながるということはあり得ると思います。
* 森口千晶とエマニュエル・サエズの研究より。(『日本社会のしくみ』p.41より引用)
** 大竹文雄・森口千晶「年収580万円以上が上位10%の国 なぜ日本で格差をめぐる議論が盛り上がるのか」(『中央公論』2015年4月号。『日本社会のしくみ』p.41、p.91より引用)
*** 2016年の国税庁「民間給与実態統計調査」より小熊氏が割り出した数字(『日本社会のしくみ』p.41より引用)。
**** 後藤道夫「『下流化』の諸相と社会保障制度のスキマ」(『POSSE』30号、2016年3月。『日本社会のしくみ』p.42、p.92より引用)
「日本」を語る人の多くが大企業型に属している
ただ、そうはいっても、よりきついのはやはり残余型の人たちでしょう。 残余型は増加傾向にあり、経済的にも精神的にも追い込まれて、引きこもりや自殺など深刻な状況に置かれている人も少なくありません。
にもかかわらず、残余型の生活の苦しさには社会の関心があまり向けられない。「日本」という国の制度や仕組みを論じる時、通勤電車の混雑解消だとか保育園の拡充が必要だといった具合に、大企業型の生き方を念頭に置くことが多いけれども、それは語り手の多くが大都市のメディア関係者であり、大企業型に属しているからなんでしょうね。
大手のテレビ局に勤めている人なら、有名大学を出ていて、年収も高い人が多いでしょう。会社の同僚も同じような人ばかりでしょうから、自分たちの抱える不満や不安が世の中の標準だと思ってしまう。出版社や新聞社もそうですし、本を買う人も、ものを論じるのもそういう人が多い。
そうすると、日本人のライフスタイルというのは、郊外に家があって専業主婦がいて、共感を得やすい問題というと保育園が足りなくて子育てに苦労していることだと考える。メディアが横並びすることで、そういうイメージがさらに肥大して流布されることになります。
想像力が働かないことが分断の根源にもなっている
大企業型とそれ以外という、違う生き方をしている人たちが出会う機会もほとんどないですよね。コンビニエンスストアの店員とお客という関係性で接することはあったとしても、相手がどんな生き方をしているか、どんな価値観を持っているかといったことを話すことはまずない。都市部に住む人と地方に住む人も、それほど交流があるわけでもないですし。
要は、自分と違う類型の人々の境遇に対して、想像力が働かないわけです。想像力が働かないと相手の立場も理解できない。それが分断の根源でもあると思います。
そう考えると、個々人がもう少し想像力を働かせることのできる世の中であってもいいですよね。自分たちの狭い行動範囲と狭いスパンの中で経験していることだけが、人間の生き方ではないのだと認識する。他の社会に行けば、見た目の違いもあるけれども、かなり違う原理で動いているという社会も多いです。日本だって、100年さかのぼれば社会の価値観も制度もかなり違うわけですから。そういうことに思いが至れば、生き方や働き方は画一化できるものではないと分かるし、他者への想像力も湧いてくるのではないかと。
そういう視点に立って、自分の、あるいは自分たちのやっていることを、もう一回見直してみる。そのうえでもう少し柔軟に考えていくという姿勢が必要だと思います。
WEB限定コンテンツ
(2019.9.17 小熊氏の自宅にて取材)
text: Yoshie Kaneko
photo: Kazuhiro Shiraishi

小熊英二(おぐま・えいじ)
1962年東京生まれ。東京大学農学部卒。出版社勤務を経て、東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。現在、慶應義塾大学総合政策学部教授。学術博士。主な著書に『単一民族神話の起源』(サントリー学芸賞)、『<民主>と<愛国>』(大佛次郎論壇賞、毎日出版文化賞、日本社会学会奨励賞)、『1968』(角川財団学芸賞)、『社会を変えるには』(新書大賞)、『生きて帰ってきた男』(小林秀雄賞)、A Genealogy of ‘Japanese’ Self-Imagesなど。
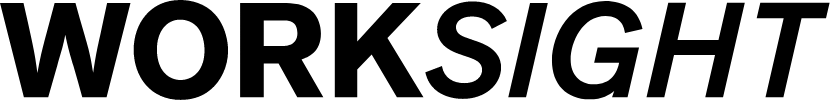
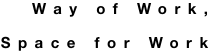
![働くしくみと空間をつくるマガジン[ワークサイト]](/images/common/ttl-catch_copy-002.png)




FacebookでWORKSIGHTを購読
TwitterでWORKSIGHTをフォロー
RSSを購読する