Foresight
Oct. 12, 2020

働くことは苦しみか、喜びか。労働観の歴史的変化を読み解く
「家業」に端を発する日本独自の労働観
[水町勇一郎]東京大学 社会科学研究所 教授
いまの日本社会では、仕事に楽しさや喜び、やりがいを見出したい、あるいは働くことを通じて価値観や自分らしさを追求したいと思っている人が多いと思います。
ただ、世界の歴史を振り返ると、人間が文明を築いて以来、労働は長く苦しみと見なされてきました。労働が肯定的にとらえられるようになったのは、ごく最近のことです。
古代ギリシャからローマ時代まで、労働は苦しみとされた
ヨーロッパ文明の原点である古代ギリシャでは、生きるための糧を得るために活動することは動物が生きるために獲物を捕まえることと同一視され、不自由で非人間的な卑しい行為と考えられていたのです。
当時の人々が考えた、人間的で自由な活動とは「真・善・美」にまつわるものです。「真」は真実を追求すること、つまり哲学です。「善」は善いことの探求・実践ということで政治的活動であり、「美」は美しいものを眺めてきれいだなと感じること。こうした行為が自由を体現し、人間の存在価値を明らかにするものだと考えられてきたのです。苦しいものである労働は、戦争で負かした人を奴隷にして押しつけていました。
これがローマ時代になると、働くことの価値観が宗教の中に埋め込まれていきます。この時代に発展したキリスト教の旧教であるカトリックでは、聖書の中で、働くことは人間が生まれながらにして持っている罪を償うための罰であると位置づけました。
具体的には、アダムとイヴが神に禁じられたリンゴを食べたことで、男であるアダムは食べものを自分で耕して作るという罰が与えられ、女のイヴには妊娠・出産の苦しみが与えられた。英語のlaborに「労働」と「陣痛、分娩」という意味があるのは、その教えを受けてのことです。罪を償うために、人間はそうした苦しみを引き受けなければならないとされたわけで、この文脈において働くことは苦しみと見なされていたわけです。
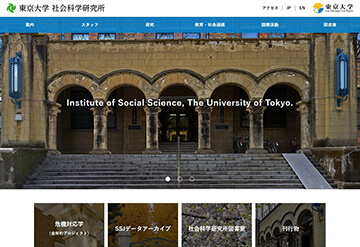
東京大学 社会科学研究所は法学・政治学・経済学・社会学の4分野にまたがる総合的な社会科学の研究所。1946年8月に設立された。https://jww.iss.u-tokyo.ac.jp/
プロテスタンティズムが労働観を一変。資本主義大国アメリカを形成
労働は神から与えられた罰であり、人間にとって苦しい活動であるというこの考えは、古代ギリシャからローマ・キリスト教を通じて中世まで続きました。しかし16世紀にルターやカルヴィンが主導した宗教改革で大きな転換を迎えます。
ルターらは免罪符を買って贖罪を得るという風潮を批判して、カトリック教会の腐敗を正したわけですが、このとき同時に働くことは神から命じられた「自由な行為」であると主張しました。カトリックと真逆の労働観を提唱し、社会に植えつけたのです。
月曜から土曜まで一生懸命働いて日曜日に教会で祈りを捧げれば、神から救いの確証が得られるというのがプロテスタントの教えです。真面目に働くことが良いことなんだ、神様から与えられた仕事なんだと示した。ここでいわれるのはlaborではなく、ドイツ語の“Beruf”、日本語でいうところの「天職」です。職業は神から与えられたものということで、禁欲的に働くことに人々が意味を見出すようなります。
その後、勤労を良しとするこの価値観がドイツからイギリスへ渡っていきます。真面目に働こうという風潮の中で産業革命が起こり、さらに新大陸であるアメリカへとこの考えが伝播していきました。
アメリカはプロテスタントが作った国です。自分で働いて耕した土地は自分のものになるということで、東海岸から入って西海岸へ、さらに太平洋へ突き抜けてハワイにまで領土を拡張するに至りました。マックス・ウェーバーが言うように*、勤労を奨励するプロテスタンティズムの倫理に基づいた近代資本主義がアメリカで大きく花開くわけです。
* マックス・ウェーバー『プロテスタンティズムの倫理と近代資本主義の精神』(岩波書店、大塚久雄訳)
相反する労働観が働くことに対する意識を多様化している
こうして俯瞰すると、働くことの価値や意識が宗教の発展とともに変化したこと、とりわけカトリックとプロテスタントで大きく変わったことが分かります。真面目に働くことがいいことだという考えは、ヨーロッパでは16世紀以降に生まれた1つの流れに過ぎないということです。
働くことに対する考え方の違いはいまも根強く残っていて、カトリックの影響が大きい国であるイタリアやスペイン、フランスなどでは仕事に縛りつけられることを嫌う傾向が見られます。仕事は定時で終えて、残業も時間外労働もしない。働くのは夏のバカンスを楽しむため。労働は罰であり、なるべく逃れようという意識があるわけです。
一方、プロテスタントの影響が大きい国であるドイツやアメリカでは真面目に働くことがいいことだという意識が強い。働いた分、新しい財産を得られるというのは、まさにアメリカン・ドリームですよね。
ですから、いまでもやはりカトリック的な考え方とプロテスタント的な考え方があって、そのバリエーションが働くことに対する意識を非常に多様なものにしているのです。

家族や世の中のために働くという考えが
日本の労働観の中核にある
翻って、日本はどうでしょうか。
欧米の労働観が宗教と密接に関係しているのに対して、日本の労働観の根底にあるのはイエの理念であり、ムラ社会やイエ社会のしがらみが色濃く反映されています。
例えば、江戸時代には働くことは「家業」として認識されていました。家業には、家族の生活手段を得るための「生業(なりわい)」と、社会に対して自らの役割を果たす「職分」という2つの側面があります。
このうち職分についていえば、江戸時代には士農工商という身分階級がありましたが、武士という支配階級だけでなく、被支配階級である農民、職人、商人も、それぞれ社会の中で身分を与えられている。それを一生懸命果たすことが、働くこととして意味があることとされました**。
このように、家族のため、世の中のために一生懸命働くという考え方が日本の労働観の中核をなしているわけです。
** 石門心学を開いた石田梅岩はこの職分観を「四民の職分」と呼び、士農工商それぞれの階級で真面目に自分の仕事を果たすべきだと説いた。この考えは道徳観、宗教観としても民衆の間に広まり、結果的に与えられた身分を正当化・固定化して、政治機構の安定化にもつながったと水町氏は指摘する。
企業のために働くことがエトスとなり高度経済成長をもたらした
江戸幕府が崩壊して身分制度がなくなった後でも、家族のために働き、社会から与えられた役割を果たそうという労働観が人々の間に根強く残りました。
それは「富国強兵」「立身出世」という言葉に見て取れます。農民の子も商人の子も、尋常小学校に行って勉強して、家族のために働いて身を立てることが奨励されました。明治、大正時代には先進諸国に追いつくため、国をあげて勉強や労働に勤しんだわけです。
戦後の高度経済成長期には、社会におけるイエの役割が、会社・企業共同体にシフトしていきます。高度経済成長の中で企業共同体が家族的な存在にすり替わって準イエのような位置づけとなり、会社は家族なんだという意識が広がっていった。終身雇用制度もその意識を強化しました。
そんな状況でいつしか企業が疑似家族のように見なされ、“家族”である企業のために働くことがエトスとなって高度経済成長をもたらしたと考えられます。
何のために働くかを考えないまま、グローバル競争に突入
個人の自由を重視して、労働をなるべく避けようとするイタリアやフランスのような国があり、他方、真面目に働くことがいいことだとするドイツやアメリカのような国もある。日本はそもそも労働観の成り立ちが違うので、欧米各国と同列に論じることはできませんが、世間や会社のために懸命に働こうという意識は、ドイツやアメリカよりもっと強いと思います。
しかしその結果、真面目に働くことそれ自体が目的化しまったことは否めません。何のために働くか、自分は何を大事にしたいと思っているのかということを考えないまま、企業という組織に絡め取られてしまっている。
そしてそのまま1990年代のグローバル競争に突入してしまったことが、いまの日本の労働環境を息苦しくしている1つの要因だと思います。
働き方改革とコロナ禍で、労働環境は大きな転機を迎えている
高度経済成長期は人口が増加していたので、組織に人がどんどん入ってきました。でもいまは少子化で若い人が入ってこない。なのにグローバル化でノルマや競争を強いられ、仕事は増える一方です。
そんな状況で自分は何のために働いているのかという価値観を意識できないまま、企業の論理で働かされ続けた結果が、ワークライフバランスの欠如、メンタルヘルスの不調、さらには過労死や過労自殺を生んでいるのではないでしょうか。
こうした日本の労働環境は健全ではないし、抜本的に変える必要があるということで、いま取り組みが進められているのが働き方改革です。加えて、デジタル化やアフターコロナを見据えて、まさにいま働き方は大きな転機を迎えています。次回、その実情について詳しく話します。
WEB限定コンテンツ
(2020.8.7 文京区の東京大学 社会科学研究所にて取材)
text: Yoshie Kaneko
photo: Rikiya Nakamura
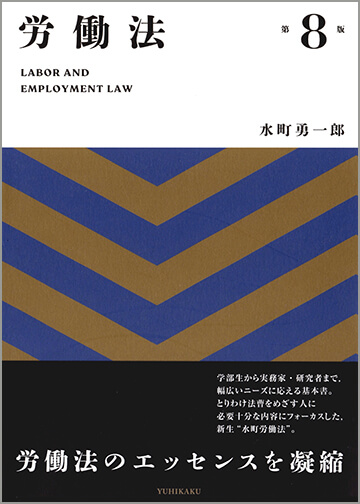
水町氏の著書『労働法 第8版』(有斐閣)では、法改正や判例の最新の動きも反映し、時代に合わせて変化する労働法の理論と実態を分かりやすく解説。事例が豊富に紹介され、初心者にも読みやすい。

水町勇一郎(みずまち・ゆういちろう)
東京大学社会科学研究所教授。1967年佐賀県生まれ。1990年東京大学法学部卒業。2010年4月より現職。専攻は労働法学。主著に『集団の再生―アメリカ労働法制の歴史と理論』『「同一労働同一賃金」のすべて 新版』『労働法 第8版』(以上、有斐閣)、『労働法入門 新版』(岩波新書)、『詳解 労働法』(東京大学出版会)ほか。
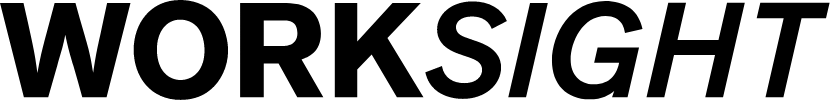
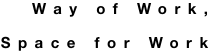
![働くしくみと空間をつくるマガジン[ワークサイト]](/images/common/ttl-catch_copy-002.png)




FacebookでWORKSIGHTを購読
TwitterでWORKSIGHTをフォロー
RSSを購読する