Foresight
Oct. 28, 2013

“quality of working life”――社会貢献が“働くことの質”を高める
ソーシャル・ビジネスを成功に導くために求められるもの
[谷本寛治]早稲田大学商学学術院 商学部 教授
前回の記事で、どんな企業でもソーシャル・ビジネスを手がけることは可能だと話しました。しかし、一般の企業がやみくもに社会貢献しようと思っても空回りするだけです。事業として結果が出ないばかりか、企業のイメージアップにもつながりません。
まず注意したいのは、取り組む社会課題がその会社のコアのミッションにひもづいているかどうかということ。投資家や金融機関は儲けるために資金を提供しています。そういうステイクホルダーに対して単純に総花的な寄付をしても、成果も評価も得られません。会社のミッションと離れた活動はわかりにくく、顧客からも投資家からも評価されません。
自社のプレゼンスを高めつつ、社会貢献も果たそうとするときは、「なぜこの会社が」「この取り組みをしているか」が明確であること、理解を得ることが必要です。「わが社の経験を活用して社会のこんな課題を解決したい」「環境問題にこんな可能性を開くために自社の技術を活用する」といった具合に、既存の事業の一部でいいので社会の課題とリンクしていることを明示することが重要です。
コラボレーションのためにオフィスを出よう
では、その糸口をどう見つけるかというと、主役は経営者でもマネジメント層でもなく、まずは現場の担当者だと思います。特にCSRやコーポレートコミュニケーション、IR、広報といった部門の人達ですね。彼らが外部の様々な動きを敏感にとらえて、社内に的確なフィードバックをすることがまず大前提です。
市場や顧客層の動き、NGOの次の動き、新しいガイドラインのポイント、IRなら株主の動きなど、社会や環境にまつわる情報を入手して、社内の言葉に翻訳し、役員や他の現場のメンバーに的確に伝えます。市場社会が自社をどう見ているか、何を期待しているのかを実感として持つことが重要でしょう。
NGOやソーシャル・エンタープライズなどで、ユニークな事業を行っている人達と接点を作り、いろいろな活動を見聞きする中で、ふさわしい課題やアイデアを見つけ出す。先ほど挙げたような部門にいる人達は、積極的に外での集まりや関連する講演会などに足を運んでほしいと思います。とくに会合の後の社交の場を活用し、さまざまな人と知り合い、ネットワークを広げていく。オフィスに閉じこもったままでは、いい出会いやコラボレーションなんてできません。
よく知られた例を挙げると、ボルヴィック*はユニセフと連携して、商品の売上1リットルにつき途上国で10リットルの水を井戸から掘り出すというプログラムを行っています。ボルヴィックだから水、とつながっていくイメージがあって、その会社ならではの活動として説得力があります。また、アサヒビールの「うまい!を明日へ!」プロジェクト**は、スーパードライ1本につき1円を、各地域の環境保全活動などに寄付するというもので、世代を超えて、支持されました。実際に売上も上がり、消費者の共感を得ていることがうかがえます。
担当の思いだけで突っ走っては社内は動きません。ボルヴィックやアサヒビールにならって、「うちでも寄付付き商品を手がけよう」と考えたとしても、実際には、営業から生産、広報、マーケティングなどと連携できないと、この手のキャンペーンはうまくいかない。仕組みだけ真似して作っても、寄付は集まらないし、自分達の会社も何の成果も得られずに終わってしまいます。 だから現場の担当者には、社外の情報を仕入れつつ、社内の意向やアイデアをまとめて伝えていく、そんな情報のハブのような役割が求められるといえそうです。
*ボルヴィックとユニセフの連携
ボルビックは「1L for 10L」プログラムと称して、ボルヴィック商品1リットルの売上ごとに清潔で安全な水10リットルが発展途上国の住民に供給されるよう、売上の1部をユニセフに寄付するキャンペーンを毎年行っている。手押しポンプ付の深井戸の新設、故障していた井戸の修復、ソーラーパネルを利用した給水設備の建築などに貢献しており、過去6年の取り組みで36億リットルを越える支援が実現した。
http://www.unicef.or.jp/partner/event/volvic/
**アサヒビール「うまい!を明日へ!」プロジェクト
スーパードライ1本につき、1円が自然、環境、文化財などの保護、保全活動に役立てられるプロジェクト。過去6回実施し、累計寄付額は20億円を超える。
http://www.asahibeer.co.jp/superdry/umaasu/

社会のサステナビリティに
自社の事業がどれだけ貢献できるか
突き詰めていえば、社会のサステナビリティに自社の事業がどれだけ貢献できるか、そこに企業のサステナビリティがかかっているんです。そのつながりを探るには、自分は何のために働いているのか、この仕事はどういう結果につながるのか、この会社は社会の役に立っているのかという根本的な問いがなければなりません。
“meaning of working life”=働くことの意義を明らかにすることが、“quality of working life”=働くことの質の向上につながります。この意義が働く一人ひとりの中で問われていないと、仕事を客観視できなくなって、組織の中に埋没してしまう。「組織の論理とは何か」って、実ははっきりしない。そのあいまいなものに流され、不祥事を起こしてしまうこともある。これまでにないアイデアや取り組みを面白いと思って、みんなで議論する。それができない職場では社会課題の解決やイノベーションは望むべくもないでしょう。
従業員一人ひとりが働くことの意味をしっかりとらえている会社は、みんな生き生きしているし、仕事自体を楽しんでいます。だから新しいアイデアも可能になる。アウトドアスポーツ用品・ウェアのパタゴニア***は、そういうものがうまく機能している会社だと思います。パタゴニアでは、波が来たら仕事中でもみんなサーフィンに行っちゃうんですよ。自由でオープンな働き方ができるような仕組みがあるんです。社会貢献の意識も高くて、社内にはいつしか託児所ができました。1人が仕事場に子どもを連れてきて、それが2人、3人と増えて、ついに保育士を雇うことになったんです。
制度を先に作ったのではなく、社員の実態とニーズが先にあった。「ここで働きたい」というモチベーションが社員達にあり、オフィスにも行動を制限する敷居がないからこそ、みんなが環境や社会によいビジネスのあり方について意見を出しあい、具体的な解決策が生まれてくる。結果、自由に働き続けることができるわけです。
社員同士で課題を共有して、オープンで議論できる風土作りは非常に重要です。それは仕事の質を高めて、新しいことを考えたり挑戦しようとする意欲を促します。そういう組織風土の中で自分の存在を示そうとしたら、勉強し自分を高める努力も必要です。広いパースペクティブを持ち、多様なネットワークをもっていないと、何も貢献できません。
働き方を硬直させる「制度の落とし穴」
残念なことに、日本では制度だけ作って安心してしまう企業が多いように思います。ボランティア休暇制度や介護休暇制度など、制度を作っても、「休んだら職場のみんなに迷惑がかかる」というプレッシャーが存在していて、結局休めない。また、休んだ場合の制度的な補完も用意されていない。そのような状況では休暇制度を利用できない。それでは働き方を変えることはできません。これは「制度の落とし穴」と呼べます。これではいい組織はできません。制度と一緒に、予算や人員の配置の柔軟性を高めたり、管理者のリーダーシップが発揮できるように体制を整える必要があります。
社会や環境のクオリティをどう高めるか。あるいは働く人達の働きがいを組織としてどう示すのか。いい仕事をして、世の中によりよい価値を提供して、顧客満足を上げていく。それが企業価値を高めていく。そんなストーリーが語られるようになってきました。その意味でも組織が柔軟に動き、コミュニケーションできるような風土を作ることが重要なんです。
企業のミッションと、今問われている社会・環境の課題、今後展開しようとしている事業領域をつなげて、一つの流れを社内で作って示す。これは簡単ではありませんが、とにかく社内で議論を重ねて、説得力のあるストーリーに編み上げることができないと、社内外への発信は難しいでしょう。
社会のサステナビリティにいかに貢献していくかを企業活動のベースに据える三菱ケミカルホールディングスや、水の資源管理に注力するサントリーホールディングスなど、はっきりした戦略を示す先駆者も現れています。
CSRが深化するこれからの時代、余裕があるからCSRに取り組む、社会貢献をするというのではなく、そこに持続可能なビジネスの戦略を置けるような会社になっていかないと、新しい可能性に発展していきません。社会の持続性というところに自分達の新しいターゲットを持っていって、次の10年、20年を見据えた新しい仕組みをどう作っていくか。それを問われているのは企業であり、働く人一人ひとりでもあるのです。
WEB限定コンテンツ
(2013.7.22 早稲田大学構内の研究室にて取材)
***パタゴニア
カリフォルニアに本社を持つアウトドアスポーツ用品・ウェアのメーカー。代替エネルギー、森林、資源採取、持続可能な農業、有害物質/核問題、水域/海洋など様々な分野で環境助成金プログラムを積極的に行っている。創業者兼オーナーのイヴォン・シュイナードは著書の中で(Let My People Go Surfing(社員をサーフィンに行かせよう)という経営論を展開。
http://www.patagonia.com/

谷本寛治(たにもと・かんじ)
早稲田大学商学学術院商学部教授。1955年生まれ。大阪市立大学商学部卒業。神戸大学大学院経営学研究科博士課程修了。1989年経営学博士。和歌山大学経済学部教授などを経て、1997年一橋大学商学部教授。2000年一橋大学大学院商学研究科教授。2012年より現職。2005-09年特定非営利活動法人ソーシャル・イノベーション・ジャパン代表理事。2009-12年社会・経済システム学会会長。2010年ベルリン自由大学客員教授。2011年企業と社会フォーラム(JFBS)会長。著書に『責任ある競争力』『ソーシャル・イノベーションの創出と普及』(いずれもNTT出版、2013年)などがある。
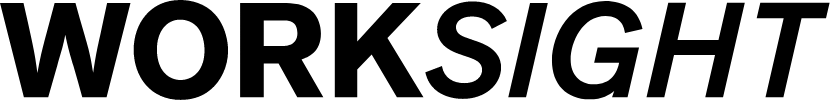
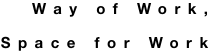
![働くしくみと空間をつくるマガジン[ワークサイト]](/images/common/ttl-catch_copy-002.png)



