Foresight
Apr. 10, 2017

いま、オフィスは第四の波を迎えている
人が集まる仕掛けがこれからのカギ
[ジェレミー・マイヤーソン]ヘレン・ハムリン・センター・フォー・デザイン、RCA 特任教授
私はもともと建築とデザインを専門とするジャーナリストでした。特に関心があったのが「オフィス」です。活動を始めた1970年代後半、多くの人々が1日の大半を過ごす場所であるにも関わらず、オフィスは小売や公共の建物に比べてはるかに注目度が低かった。そこに焦点を当ててみたいと思ったのが、そもそもの動機でした。
ビッグバンでロンドンが世界のオフィスデザインの中心に
オフィスへの興味をさらに掻き立て、より深く探求したいと考えるようになったのは1986年の出来事がきっかけです。この年に私は雑誌『デザインウィーク(Design Week)』を立ち上げたのですが、同年にイギリスで財務規制緩和、いわゆるビッグバンが起こり、世界中の金融機関がロンドンに集まってきたんです。その結果、ロンドンは世界のオフィスデザインの中心となりました。
デザインウィークの取材を通じて、ノーマン・フォスター、リチャード・ロジャーズ、フランク・ダフィー、ジョン・ワーシントンといった、ワークプレイスデザイン理論の形成に多大な影響を与えた建築家と出会うことになり、もっと勉強したい、専門家としてこの分野を極めていきたいという思いが募っていったんです。
そこで母校のロイヤル・カレッジ・オブ・アートに戻って2年間の修士課程を修めました。修士論文のタイトルは「仕事の美学」です。倫理観が仕事の美学にどのように影響していたのか、そしてそれが仕事の未来にどうつながっていくかを論じました。そうやって学問の世界にも活動の場を広げてきたわけです。
ユーザー指向のソーシャル・デモクラティック・オフィス
これまでのワークプレイスの変遷を振り返ると、大きく3段階に分けられます。
第一の段階はフレデリック・テイラー* が唱えた科学的管理法にマッチする「テーラリスト・オフィス」です。産業革命期に多く見られたもので、いってみれば効率追求型ですね。工場や機械設備の生産性を高めるには適していますが、あまりユーザー指向とはいえません。ただここには、管理する人もされる人も同じ空間と時間の中で働くことに対する倫理的枠組みがありました。それは重要であると思います。
戦後、第二の大きな変化の波が押し寄せます。効率ではなく、人々のコミュニティを重視する「ソーシャル・デモクラティック・オフィス」です。
当時、ヨーロッパ、特にドイツ、オランダ、スカンジナビアなどの北部では人手不足が続いていました。職場の管理者は工場や鉱山との人材獲得競争に打ち勝つため、より高い賃金ではなく、より良質の労働環境を提供しようと考えました。そこで社会的なネットワークや人と人の相互関係を考慮した居心地のいい楽しい環境――すなわち校舎のデスクのような画一的配置でなく、人が働きやすいレイアウトが求められるようになったのです。オフィスのユーザー指向への転換がここで行われました。
ソーシャル・デモクラティック・オフィスが生み出したのは、キャンパスのような環境です。池や噴水、大通り、中央アトリウム、植栽といった、多彩な要素で構成することができます。グラクソ・スミスクラインのロンドン本社はその1つで、中央通りがあり、広場があり、店舗がある。街としてのオフィスであり、社会的なコミュニティといえます。ストックホルム郊外のSAS(スカンジナビア航空)本社もそう。1988年にニールス・トルプが設計したもので、ソーシャル・デモクラティック・オフィスの青写真となりました。さらにさかのぼれば、1974年にオランダで建てられた、ヘルマン・ヘルツベルハーの手による保険会社セントラルビヘーアのビルもあります。
また、仕切りを設けずにオープンな空間を提供するオフィス・ランドスケープも、ソーシャル・デモクラティック・オフィスの非常に良い例です。
日本では今でもソーシャル・デモクラティック・オフィスよりテーラリスト・オフィスが多く見受けられるように思います。信頼関係の構築より監督のしやすさに重きを置く日本らしい、マネジメント上の倫理的配慮がうかがえます。
デジタル技術を使って人を追跡するネットワークド・オフィス
第三の変化は2000年代に入ってから起きました。「ネットワークド・オフィス」の台頭です。
人々はスマートフォンやタブレットを活用して、いつでもどこでも仕事ができるようになりました。ワークスタイルの変化はオフィス設計の性質も劇的に変えます。それが、オフィス内のヒトとモノをネットワークでつなぎスマート化するネットワークド・オフィスを生んだのです。
デスクスペースは狭くなる一方で、広いホスピタリティスペースが確保されるようになりました。それもバーやホテルラウンジのようなラグジュアリーな空間です。というのも、ネットワークド・オフィスでは、単にデスクに座るためでなく、人と会うためにオフィスにやってくるからです。モバイル端末があれば、どこからでもデータにアクセスできるわけですから。
世界の人々とテレビ電話会議をするために大きなスクリーンも導入されていますね。これからはIoTですべてがつながる時代です。オフィスもそれに見合った変化を遂げているわけです。
このオフィスの例としては、アムステルダムにあるデロイトの新社屋、通称「ザ・エッジ」が挙げられます。非常にハイテクな建物で、何千個ものLED照明がインターネットとセンサーにつながって建物内の人々の動きを感知・追跡できます。ネットワークオフィスでは、人と人との信頼が希薄になります。テーラリスト・オフィスでは人が人を監視していましたが、ネットワークド・オフィスではデジタル技術を使って人を追跡しているわけです。
パリにあるシュナイダーエレクトリックのザ・ハイブも一例です。エネルギー効率と快適さを両立するビル管理システムです。
ハイテク企業がネットワークド・オフィスにいるとは限らない
ソーシャル・デモクラティック・オフィスとネットワークド・オフィスの両方の特徴を備えたものとしては、グーグルやフェイスブックのオフィスがあります。
グーグルのオフィスはどちらかというと、ソーシャル・デモクラティックな要素が強いと思います。グーグラー達を大事にして、みんなが集まる場を作ろうとしていることの表れでしょう。また、グーグルでは社員の飲食に重点を置き、1日に100,000食を作ります。彼らはデータ分析に多くの時間を費やすので、社員が建物から出なくても充実した食生活を送れるように配慮しているのだと思います。
そういう意味では、ハイテク企業より経営コンサルティング企業の方がネットワークド・オフィスを形成しやすいといえます。例えば、アクセンチュアのオフィスはどちらかといえばネットワーク型ですね。コンサルタントには社内コミュニティに参加するより、表に出て稼いでほしいからです。逆にソフトウェア開発者やプログラマーはコミュニティ参加志向が強い。皮肉なことに、ハイテク企業だからといって必ずしもネットワークド・オフィスであるとは限らないんです。

ヘレン・ハムリン・センター・フォー・デザイン(Helen Hamlyn Centre for Design)は、人間中心のデザインとイノベーションをテーマに、企業や団体とも連携しながら研究活動やデザイン提案を行っている。1999年1月、ヘレン・ハムリン財団の支援を受け、RCA(イギリス王立芸術大学院:Royal College of Art)内に創設された。
http://www.hhc.rca.ac.uk/
* フレデリック・テイラー
アメリカの経営学者。
ワークサイトでは、グラクソ・スミスクラインのアメリカ本社(フィラデルフィア)を取材している。こちらもソーシャル・デモクラティック・オフィスの一例といえそうだ。
「製薬業界の常識を超える透明性が結果重視のつながりを作る」
ハイブ(HIVE)はHall d’Innovation et Vitrine d’Energiesの略。シュナイダーエレクトリックはこのビルを、建物のオートメーションシステムとエネルギーに関する自社ソリューションのショーケースと位置付けている。
ワークサイトでは、グーグルのニューヨーク支社を取材している。
「自由と明確な目標が生産性を最大化する」

オフィスというひとつの容れ物ではなく、
スペースのネットワークを持つという考え方
ネットワークド・オフィスは企業空間の縮小と柔軟な空間の拡大という側面を持っています。いつでもどこでも仕事ができる状況が整い、大きなオフィスを人でいっぱいにする概念は時代遅れになりつつあります。その流れで大企業は一部の社員をコワーキングオフィスに配置するようになりました。建物を長期契約で借りて内装にお金をかける代わりに、柔軟に使えるスペースをたくさん用意するのです。
そうすると、例えば短期間のプロジェクトでは技術チームをコワーキングスペースに置き、終わったら別の場所に移動させるといった自由度の高いオフィスデザインが可能になります。オフィスというひとつの容れ物ではなく、スペースのネットワークを持つという考え方です。グーグルのキャンパスロンドンやSAPがシリコンバレーにオープンしたカフェ「HanaHaus」などに見られるように、自社オフィスを持っていても外部の共同スペースを利用する現在のトレンドは、こうした発想が軸にあると考えられます。
そもそもソーシャル・デモクラティック・オフィスは、より人間的な職場環境を提供し、コミュニティを創造するという高い理想を持っていました。しかしこれが希釈され、概念だけを使って平凡でつまらないオフィスが多く作り出され、低いレベルのミッションと低いサービス提供の企業キャンパスが増えてしまったという経緯があります。
コワーキングスペースの中には高度なサービスを提供しているものがあり、それらはソーシャル・デモクラティック・オフィスの欠点を補います。動線がたくみに設計され、素晴らしいコーヒーがあって、有能なコンシェルジュがいて、3Dプリンタのサービスを提供していたりする。さらには、テクノロジーのスタートアップやベンチャーキャピタルを集めるといった高度なミッションを持つものもあります。それはビジネスの推進力になり得ます。
働き方は再び変化する。したがってオフィスも変化する
ソーシャル・デモクラティック・オフィスは、建築物という「箱」の内部環境を心地よく、しかも働きやすいように整えていくことで実現します。人々は機能性と快適性を追究し、ランドスケーピングを追究し、空間設計、インテリアデザイン、家具、照明を洗練させてきた。目の前にあるモノを改善するという意味で、それはシンプルな企てでした。
しかし突然、グローバリゼーションにより、タイムゾーンの異なる世界の人々と仕事をするようになりました。オフィスには物理的に存在する人もあれば、デジタル的に存在する人もいます。地球の裏側にいる人と電話するには夜遅くまで待たなければなりません。全てのメンバーが同じ空間にいた時代のようには、ことがシンプルに運ばなくなりました。
ネットワークド・オフィスはそうした問題の解決策をもたらすものでもあります。コストをより良くコントロールし、スペースを最適化するチャンスを与えてくれます。社員の行動に応じてスペースを再構成する柔軟性の高いオフィスは、さまざまな価値をもたらしてくれるのです。
とはいえ、ネットワークド・オフィスがオフィスの最終形かといえば、そうではないでしょう。働き方は再び変化しますし、したがってオフィスも変化するはずです。人間の仕事は1000年続いていますが、現代のオフィスの歴史はわずか150年に過ぎません。家内制手工業の時代には人は自宅で働き、産業革命期は工場で働くようになりました。オフィスは時代の技術によって支配されるものであり、仕事の連続体の中のほんの一部でしかないのです。
都市から独立せず、都市と深く関係するフュージョンオフィス
いま我々は生活と仕事の関係を問い直す大事な局面に立たされています。どこでも仕事ができるということは、自分自身がオフィスであり、自分が仕事と一体化しているということです。企業は社員の全て、人間としての全てに目を向ける必要があることを認識すると同時に、多額のお金をかけてオフィスビルの中に街を再現する必要がないことに気づき始めました。すぐ外には都市があるのです。「社内に会議室を置かず、ボード・ミーティングを開く時はレストランの一部屋を借りればいい」「30人が1つのデスクを囲む必要があるのは月に一度程度なので、大きな部屋を作る意味がない」と考える企業が増えてきたのです。
この先にはネットワークド・オフィスの次の段階がやってくることでしょう。「フュージョンオフィス」あるいは「ミックス・オフィス」とでもいえばいいでしょうか。それは都市から独立したものではなく、都市と深く関係するものです。
その流れはすでに見え始めています。今の郊外の企業キャンパスは若いワーカーに不評です。彼らは店舗やレストランに近い市中心部にいたいのです。そういう声を受けて都市に戻ってくる大企業も見受けられます。知的生産性が求められる施設を郊外に築くという戦略は、今の時代にはそぐわないのです。
大手不動産開発会社の多くは、フュージョンオフィスを新しいビジネスのスキームとしてとらえています。イギリスでは ブリティッシュランド、オーストラリアでは ミルバックやレンドリースなどが取り組みを進めています。ニューヨークのハドソンヤード再開発プロジェクトでも、住宅、ホテル、小売店、オフィスを混在させて区域に新しい価値をもたらそうとしています。素晴らしいオフィスを作るだけでは不十分なのです。夕方や週末を楽しく過ごせるような、そこで働くことを誇りに思えるような、人が集まる仕掛けが求められています。
世界が足並みを揃えて一斉に変化するわけではない
ワークプレイスの進化をたどっていくと、「誰もが先駆者であり、誰もが変わっていき、誰もが変化と同じペースで変わっている」と考えがちです。 しかし実際には、日本でもイギリスでもアメリカでも、まだテーラリスト・オフィスがたくさんあると思います。
そうした企業は社員の快適さや健康維持にそれほど注意を払いません。ひたすら効率を追求します。それは古い経営モデルですが、生活と仕事の境界線をくっきりと維持できるので、例えば役所のようなオフィスには有効です。テーラリスト・オフィスはまだ存在し、それを好む人たちもいる、それはそれで何も問題ありません。
また、ソーシャル・デモクラティック・オフィスの会社も依然として多くあります。仕事は職場で行うという前提のオフィスですから、病気でも出勤しなくてはなりません。テーラリスト・オフィスよりは快適で設備も整っていますが、職場に来なければ仕事ができないという意味でネットワーク化されていません。そして、それも別に問題はありません。世界が足並みを揃えて一斉に変化するわけではないのです。
しかし、テーラリスト・オフィスとソーシャル・デモクラティック・オフィスのどちらも、空間的にもコスト的にも効率的に劣る面があることは明らかです。最先端を行く企業は実際にあり、グローバル展開する大手のオフィス開発会社はスマートビルディング技術の実用化に取り組んでいます。世界は徐々に変化している。その認識は持っておくべきでしょう。
WEB限定コンテンツ
(2017.1.27 ロンドンのヘレン・ハムリン・センター・フォー・デザインにて取材)
text: Yoshie Kaneko
photo: Saori Katamoto
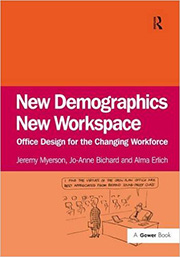
マイヤーソン氏の著作『New Demographics New Workspace: Office Design for the Changing Workforce』(Routledge刊/共著)。働き方の変化に応じたオフィスの変化を考察している。

ジェレミー・マイヤーソン(Jeremy Myerson)
ヘレン・ハムリン・センター・フォー・デザイン、RCA 特任教授。RCA(Royal College of Art)卒業後、デザインジャーナリスト、編集者として出版物『デザイン』『クリエイティブレビュー』『ワールド・アーキテクチャー』でジャーナリストや編集者として活躍。1986年に『デザインウィーク』を創刊し、初代編集長を務める。1999年にRCAでヘレン・ハムリン・センター・フォー・デザインの設立に携わり、2015年9月まで16年間指揮した。2015年10月にUnwiredと共に、未来を見据える世界的な知識ネットワーク「WORKTECH Academy」を設立。韓国、スイス、香港のデザイン機関の諮問委員会に参加。Wired誌の「英国で最も影響力のあるデジタルテクノロジー分野のリーダー100人」にも選出されている。
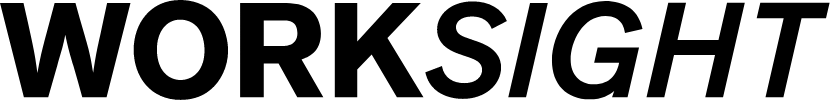
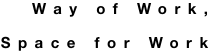
![働くしくみと空間をつくるマガジン[ワークサイト]](/images/common/ttl-catch_copy-002.png)




FacebookでWORKSIGHTを購読
TwitterでWORKSIGHTをフォロー
RSSを購読する