Management
Apr. 13, 2020

「超短時間雇用」の成功のカギは、厳密な職務定義と障害者との協働
インクルーシブ教育の推進から就労の創出へ
[近藤武夫]東京大学 先端科学技術研究センター 人間支援工学分野 准教授
前編で、週15分や1時間といったごく短い時間で障害者などに仕事を依頼する「超短時間雇用モデル」について説明しました。ここでは、企業がこれを導入する際に留意してほしいポイントをお話しします。
コアの業務と周辺業務で切り分ける
まず重要なのは、採用前に職務内容を明確に定義すること。第一歩は個々の社員の業務分析です。それぞれがどのような仕事を抱えているか、企画書作成、商談、会議、議事録作成、英訳、データ入力などに要素分解していきます。その中で、その人にしかできない仕事や成績を上げてほしいコアの部分と、それ以外の周辺業務で時間を取られて困っているものに切り分けます。
ある社員に対して上司が、主任のような立場で部内の環境調整をしてほしい、それがその社員の本務であると考えているとしましょう。その社員には上司と別の場所で、自分が認識している強みや上司からの期待を聞いていきます。そこで自分が特に注力したい仕事が上司の意向と一致していれば、それが本人の本務であると考えられます。
例えば商談や企画書作成がうまい社員Aさんがいて、本人もそれを自覚していて、そこに集中したいと考えている。上司も同じ思いで、そうしてくれると部署の成績も上がるだろうと考えている。なのに、実際にはAさんは検品やデータ入力、伝票整理といった周辺業務に最も時間を取られている。こういうことが往々にしてあるんです。
そこで、この周辺業務の内容や労働時間、給与などを細かく決めて、その後、その仕事に強みのある人材を採用していきます。「清掃」とか「軽作業」といった漠然とした表現でなく、「胃カメラの洗浄」とか「英文を日本文に下訳する」といった具合に、仕事の内容を厳密に定義するんです。
その後、求める仕事に合致した人が来るわけですから、ミスマッチは起こりにくいですよね。採用した人には定義した仕事だけをやってもらいます。他のことは頼まず、職務遂行に関係しない能力も求めないようにします。
超短時間雇用の導入をきっかけに業務改善が進むことも
実際にあった事例を紹介しましょう。プログラミングの部署で、日本語の技術文書を英訳する仕事が週5、6時間発生していたそうです。みんな忙しいので仕方なく課長さんがやることが多かったのですが、この下訳をしてくれる人を超短時間雇用で探すことにしました。
来てくれたのは発達障害と精神障害のある人で、敬語が使えません。感覚過敏もあって、ひげを剃ったり、えり付きのシャツを着たりすることができないし、ひもで締め付ける靴も履けない。だから丸首シャツにジーンズ、サンダル履きという格好で面接に現れ、挨拶も「よう! よろしく」という感じで、まあビジネスの感覚とはかけ離れているわけです。
でも、その人は英訳はよくできるんですよ。下訳の仕事に敬語は使わないし、服装にしても客先の仕事ではないので問題はない。それで採用されて、結果、満足度は非常に高いわけです。下訳はうまいし、課長がさっとチェックするだけで終わるので、短時間で質の高い仕事ができるようになったと喜んでいました。
この事例からも分かるように、本質的に必要な力は何なのかを定義することが肝心です。職務定義が難しい、面倒だと思う向きもあるかもしれませんが、このプロセスによって業務の効率化が図られますし、社員を評価するポイントを絞り込むといった副次的効果も得られます。職務定義がないということは、部下も上司も空気を読みながら仕事を進めているということ。超短時間雇用の導入をきっかけに業務改善できたという会社も多くあります。
障害者は忙しくて困っているところを助ける人材
それからもう1つ、同じ職場でともに働いてもらうことも超短時間雇用の要件です。
よくあるのが、障害のある人をどこかの部署に集めて働いてもらうという雇用形態です。「うちの企業は障害者雇用を一生懸命やっているらしいけど、どこにいるか分からない」という声はよく聞きますが、それは排除の一形態だと思います。
ですから我々は部署から引きはがすことをせず、その仕事があるところに障害のある人を埋め込んでいく形で、一緒に働いてくださいと企業の方に伝えているんです。「障害者が来るけれども何をやってもらおうか」と仕事を作るのではなく、「仕事の困りごとを解決してくれる人が来てくれた」と迎え入れるということですね。その結果がたまたま長時間働くことに難しい障害のある人だった、ということです。
障害者雇用を一生懸命やろうとか、慈善事業をやろうと思っていると、超短時間雇用はうまく機能しません。忙しくて困っているところを助けてくれる人材として障害者を見るというスタンスが一番重要で、だからこそ職務定義を厳密に行う必要があるし、それによってマッチングの精度が上がるので満足度も高まるというわけです。
ニーズがあるなら、制度上の壁はみんなで変えていけばいい
受け入れる前は不安があったけれども、実際に一緒に仕事をしてみたら意外にスムーズにいったという声もよく聞きます。日本では通常学級と支援学級で分ける教育が主流なので、企業で働く人たちは障害者と一緒に過ごした経験がまだまだ少ない。障害者が働けるというイメージがないので、雇う側の心の壁が大きいんですね。
でも、健常者といわれる人たちも、本当はみんな抱えているものがあると思うんですよ。冬になると手術痕が痛んでつらいという人もいれば、月経前症候群で苦しむ女性もいるでしょう。診断こそ下されていないけれども、うつのような状態で仕事にやっと取り組んでいるという人もいるかもしれません。
つらいときは在宅で仕事できるようにするとか、週1日の就労に切り替えるとか、場合によっては年9カ月の雇用にするとか、そういう柔軟な発想があれば、障害のあるなしに関わらず、誰もが自分のペースで働けるようになりますよね。我慢して一生懸命働くのが偉いとみんな思っているけれども、障害者と一緒に働くことで実は自分も柔軟な働き方をしたいんだということも口にしやすくなるでしょう。
ニーズがあるなら、制度上の壁はみんなで変えていけばいい。障害者雇用がそのきっかけになることもあるわけです。

東京大学 先端科学技術研究センターは、学際性・流動性・国際性・公開性という4つの基本理念に基づき、文系と理系の垣根を越えた研究活動を行っている。
https://www.rcast.u-tokyo.ac.jp/ja/index.html
近藤氏が携わる主なプロジェクト。
・超短時間雇用を含めた、インクルーシブかつ多様性を歓迎する配慮ある働き方を研究する「IDEAプロジェクト」。
http://ideap.tokyo/
・障害と高等教育に関するプラットフォーム形成事業「PHED」。
http://phed.jp
・音声教材のオンライン図書館プロジェクト「Access Reading」。
http://accessreading.org
・テクノロジーを活用して障害のある子どもたちの学習や進学をバックアップするための研究プロジェクト「DO-IT Japan」。
http://doit-japan.org

首の動きでコンピューターを操作し
有名大学を経て司法試験に挑戦する人も
超短時間雇用モデルを考案する前段として、僕は障害がある子どもたちの学びをサポートする研究をいくつか進めてきました。
「DO-IT Japan」(以下、DO-IT)は、テクノロジーを活用して障害のある子どもたちの学習や進学をバックアップするための研究プロジェクトです。障害のある子どもたちの中から未来の日本のリーダーをつくることを主眼に、小学3年生くらいから中学生、高校生、大学生、さらに就職支援まで、伴走します。
2016年に障害者差別解消法ができて学校に合理的配慮が浸透してきましたが、この法律ができる前は障害のある子が大学進学を希望しても、非常に壁が厚かったんですね。「環境が整っていない」「来てもそちらが苦労するのでは」という理由で、ほとんど門前払いです。通常の進学校で勉強したい生徒も、特別支援学校しか選択肢がなく、卒業後は地域の福祉的就労で仕事をするというルートがお決まりのようになっていました。
そんな状況を変えるため、テクノロジーを活用して障害のある子どもたちの学びや進学を産学連携で支援するのがDO-ITです。
例えば、首から下が全く動かず自発呼吸も難しいような子は、呼吸器を装着して病院で過ごすことが多かったけれども、いまなら首の動きだけでコンピューターを操作できる機器を使って勉強できます。実際、そういう子で有名私立大学の法学部に進んでロースクールに行き、いま司法試験にチャレンジしているケースもあります。
従来なら支援学級に行く子が通常学級で学べるように
「Access Reading(アクセスリーディング)」は、我々が開発・運用している音声教材のオンライン図書館です。
目が見えない、肢体不自由があってページがめくれない、発達障害で文字を認識できないなど、紙の教科書では勉強できない子が多くいます。そういう子に向けて、選択した文字を読み上げる、画面タッチでページがめくれる、フォントの拡大や変更が自由にできるといった機能を提供します。印刷物にはない多彩な機能で多くの子の学習機会が広がります。
全国の小中高の児童・生徒は、どの教科書のコンテンツも無料でオンラインアクセスできます。こうした教材やICTを活用することで、通常学級に所属しながら、部分的に特別支援教育を受けて学ぶ児童生徒も増えてきました。
「AHEAD JAPAN(一般社団法人 全国高等教育障害学生支援協議会)」も私がファウンダーのひとりで、いま100大学くらいが参加している全国規模の大学連合です。高等教育機関における障害を持つ学生の支援に関する連携・協力体制を築いています。2016年の障害者差別解消法施行を契機として、全国の大学では、さまざまな障害のある学生の支援を組織的に行う大学が一般的になりつつあります。
「PHED(フェッド/Platform of Higher Education & Disability)」は、障害と高等教育に関するプラットフォーム形成事業で、2017年から東京大学が取り組んでいる3年間のプログラムです。現在、120の大学と企業が参加していて、障害を持つ学生の大学進学や就労への移行を支えるための取り組みで協働しています。
PHEDは一般社団法人「企業アクセシビリティ・コンソーシアム(ACE:Accessibility Consortium of Enterprises) 」とも連携し、参加企業とともに新たな障害者雇用モデルの確立に取り組んでいる。
前例がないのなら自分が前例になればいい
DO-ITに参加している学生の中には、東大、京大、早稲田、慶応といった難関校に進学する人も増えてきています。それはそれで喜ばしいことですけど、難関校に進学することが我々の目的ではありません。本人が望んだ進学先を自分自身の夢として自然に選べる、選択肢が開かれた社会を作りたい。
そのために私たちが注目してきたのは、中学や高校、つまり中等教育から、卒後の中等後教育進学への移行を支援することです。本人の興味や関心を生かして社会参加するために、どのような力を培っていけばいいか。持てる力を生かすためには、障害のある子どもたちの参加を想定しない社会環境の側に存在する障壁をなくしていく必要があります。そのために、自分たちにどんな配慮があればよいか。個々の学生がそれを見出すためのサポートに特に力を入れています。
例えば、魚が大好きで将来は水族館で働きたいという子がいます。ただ、文字の読み書きが難しい学習障害を持っているので、勉強はキーボードや音声で文字を入力したり、読み上げ機能で教科書を読んだりしていました。ところがこうしたテクノロジーを使おうにも、入試では「前例がない」という理由で持ち込みが認められず、本人はもうダメだと落ち込んでしまった。本来なら魚の飼育に関係ない文字の読み書きだけで夢が絶たれるなんて、おかしな話です。
だからそこであきらめず、「前例がないのなら自分が前例になればいい。自分が第一号になればいいんだ」と励まして、その子は学校に掛け合っています。こんなふうにして毎年、何かしらの前例がDO-ITで出てきている感じですね。
ドローンのパイロットとしてメディアでも紹介されている高梨智樹くんは、彼が中学生のときから関わってきました。ヘリコプターのパイロットになる夢を抱いてきましたが、読み書きの障害があるからと、夢をあきらめかけたこともあったそうです。でもやってみようといろいろ探して、ドローンパイロットのトップレーサーになった。操作マニュアルを読んだり電波通信の資格試験のための勉強する際は、音声読み上げテクノロジーを使っています。
僕らが必要としているのは、哀れみでなく合理的配慮です。私はこれができないので、それをカバーするこういう方法を認めてくれますかと交渉するんです。学校側は前例がないのでその方法を知らない。そこで僕らがいろんな方法を、このプログラムの中で教えているわけです。
障害者の就労先が限られていると可能性が広がらない
そうやってインクルーシブ教育を進めても、最終的に障害者の就労先を多様化していかないと出口が広がりません。障害者雇用の型にはまるように子どもたちを育ててしまい、子ども自身の夢や可能性が摘まれてしまいます。
ある親御さんから相談を受けたことがあります。まだ子どもは就学前で小さいのですが、難病があるので、ある地域の福祉施設と作業所が良さそうだから、将来その子がその施設に行けるように、家族で今からその地域に引っ越したいと思っていると。親の思いとしてはあり得る選択肢です。
でも将来、その子は本当にその地域や施設に行きたいと思うだろうか。ひょっとしたら、今後学校の中で他の子どもたちと一緒にインクルーシブに学ぶ中で、あの会社で働きたい、図書館で働きたい、宇宙飛行士になりたい、花屋さんになりたいとか、実はいろいろ夢が生まれてくるんじゃないかと思うんですよね。
だけど現状では障害者の就労先が限られてしまっているために、特別支援教育の現場でも敢えて可能性を広げず、型にはめるような教育がなされてしまう。せっかく夢や挑戦したいことがあって、そこに立ち向かおうとする子がいたとしても、親や教員は安全を重視して、既存の型に当てはめるための教育になっちゃうんですよ。そうすると前例のない生き方をする子や型破りな発想のできる子は出てきませんよね。
短時間しか働けない人は障害者雇用の枠でも排除されがち
障害者には健常者と同じ仕事はできないだろうと考える人がいますが、単にその機会が与えられていないだけだと思います。
例えば東大先端研でプロジェクトマネジメントを担う職員は、筋ジストロフィーという進行性の難病を抱えています。24時間呼吸器を付けていて、介助者がいないと生活できません。それでもコンピュータが使えるし、頭の回転が速いし、効率的な思考ができるからマネジメントがうまいんです。
介助者の都合で週に5時間、関西の自宅でオンラインで仕事をしてくれます。モニターに本人の顔が表示されるロボットを遠隔操作していて、東京にいる僕らとのコミュニケーションもリアルタイムで問題なくできます。
この人はもともとはDO-ITでサポートしていた学生で、関西の有名私立大学に進んだ有能な人材です。ただ、介助者が必要で、しかも週5時間しか働けないという人は、企業ではほぼ雇用されません。障害者雇用の採用面接でも、介助者が必要と分かると、その瞬間に門戸が閉ざされる感じ。障害者雇用促進法でも、雇用できる障がい者の条件として、障害者手帳を持っていること、週30時間以上、少なくとも20時間以上は働くということが課されています。だから特定の職務なら力が発揮できる人も、週5時間だけ働きたいというような人は、雇用の対象から排除されてしまうわけです。
短時間でも働いて、社会で役割を持つチャンスを作っていく
障害の問題の裏には、子育て中の世帯や、親や家族の介護を行う必要のある世帯の排除、さらには貧困の問題なども含まれています。障害のある人たちが40歳を超えるあたりから、貧困の問題を抱えるケースが少なくありません。支えてくれる親や家族が亡くなったり、本人が病気になったりと、きっかけはさまざまです。
短い時間しか働けないという人に対して「じゃあ働かなくていいよ」というのではなく、短くであっても働ける、社会で役割を持てるチャンスを作っていくことが重要です。「うちで数時間働いてください」と気軽に頼める、そういう関係を実現する仕組みを目指しているのが超短時間雇用なんです。
学校を卒業した後の長い時間を労働社会の中で生きていくわけです。働き方を多様化していかないと、障害者を始めとするさまざまな事情を持つ人々がそこにいることを認める社会から遠ざかっていく。超短時間雇用はそこに切り込んで、社会的に大きな価値をもたらす仕組みであると考えています。
WEB限定コンテンツ
(2020.1.14 目黒区の東京大学 先端科学技術研究センターにて取材)
text: Yoshie Kaneko
photo: Kazuhiro Shiraishi

近藤武夫(こんどう・たけお)
1976年生まれ。東京大学 先端科学技術研究センター 人間支援工学分野 准教授。広島大学大学院教育学研究科などをへて現職。専門はインクルーシブな教育や雇用に関する研究。主な著書に『学校でのICT利用による読み書き支援――合理的配慮のための具体的な実践』(編著、金子書房)、監修を手掛けた本に『発達障害の子を育てる本 スマホ・タブレット活用編』(講談社)など。
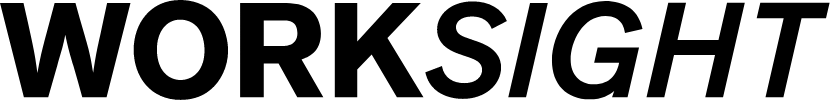
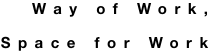
![働くしくみと空間をつくるマガジン[ワークサイト]](/images/common/ttl-catch_copy-002.png)




FacebookでWORKSIGHTを購読
TwitterでWORKSIGHTをフォロー
RSSを購読する