Innovator
Mar. 8, 2021

20世紀初頭、パリのカフェはイノベーションの起点だった
逸脱者たちのサードプレイス
[飯田美樹]カフェ文化、パブリック・ライフ研究家
カフェは、お茶を飲む、一息つく、友だちとおしゃべりするといった目的のためにあると思われがちです。しかし、カフェは単なる憩いの空間ではありません。
近代のヨーロッパ、特にパリのカフェには、街の磁場に引き寄せられた創造性豊かな人々が集いました。結果として、そこは新たな価値を創出し、さまざまな芸術運動や社会変革の中心地となりました。カフェには時代をつくり、イノベーションをも促す社会的機能も備わっているということです。
印象派やダダイズム、実存主義の「企て」の場
パリのカフェの歴史は、1686年にカフェ「プロコープ」ができたことから始まります。ここにヴォルテール、ディドロ、ルソーといった思想家が集い、啓蒙思想や社会変革について盛んな議論が交わされました。それが1789年のフランス革命につながっていきます。
その後、1870年ごろにはパリ・モンマルトルのカフェにロートレック、ドガ、セザンヌ、ルノワール、モネといった画家たちが顔を揃え、のちに印象派と呼ばれる新たな芸術運動が花開いていきます。
同じくパリ市内のモンパルナスのカフェにも詩人、芸術家、音楽家たちが集結し、ダダの創始者であるトリスタン・ツァラが「すべてのことはモンパルナスの異なるカフェで企てられた」と語るほど、さまざまなものが生み出されていきました。特に陽当たりの良いテラスのあった「ロトンド」にはモディリアーニ、藤田嗣治、キスリング、ピカソ、アンドレ・サルモンといった芸術家のほか、革命家のレーニンやトロツキーもやって来て賑わいました。
ロトンドの真向かいのカフェ「ドーム」にはサルトルやボーヴォワール、ジャコメッティら、近隣の「クーポール」はマン・レイ、ユキ・デスノス、ルイ・アラゴン、シャガール、ジャン・コクトーなど、すでに著名だった芸術家がやって来た。1939年ごろからサルトルやボーヴォワールは、モンパルナスの喧騒を避けてサン=ジェルマン・デ・プレ界隈の「カフェ・ド・フロール」を新たな根城とし、やがてフロールは実存主義の聖地として世界的にその名を知られるようになります。
“避難所”として芸術家の受け皿となったカフェ
このように17世紀から20世紀にかけてパリのカフェには革新を志向する人々の熱気が渦巻き、一時代を築くエネルギーにもなっていったわけです。
特に盛り上がりを見せたのは20世紀初頭です。当時のパリはヨーロッパにおける産業、経済、文化の中心地として勢いがあり、フランス各地をはじめ他国からも多くの人がやってきました。画家のシャガールが「私にはパリが必要だということは分かっていた」と回顧しているように、「何者かになりたい」「何かを成し遂げたい」と渇望する人は、パリに行きさえすれば夢がかなうと信じていたのです。
では、なぜ彼らはカフェに集まったのか。それにはいくつかの理由があります。
1つは、カフェが今でいうサードプレイスのように機能したからです。
意気込んでパリにやってきた芸術家の卵たちですが、画壇の主流派で構成されるアカデミーや上流階級が集うサロンに居場所はありませんでした。特に印象派の初期は、彼らは世間から「おかしな絵を描く逸脱者」とレッテルを貼られ、蔑視されていたからです。
当時の主流派から見れば理解できない作品を描いていた、それこそまさに革新であることの証といえますが、ともあれ社会に彼らの居場所がなかった。そこで仕方なく“避難所”としての第三の場を求めたときに、受け皿となったのがカフェだったということです。
リソースの幅広さが人を集めるミクストユースの一面も
ここで説明した3つの要素、①「何者か」になりたいという思いがあること、②周囲の人たちとは異なる価値観を持っていて、それゆえ周囲から理解されず孤独を感じていたこと、③だからといって周囲に迎合せず、自分を認めてくれる居場所を求めたこと――これらはカフェに通った創造性豊かな人々に共通しています。
私はパリの国際政治の専門学校に留学経験があるんですけれども、パリはフランス語を話さない人には排他的なところがあって、来たばかりの外国人の多くは身の置き場がないんですね。次第に自分のことを価値のないものと思うようになる、いわゆる「パリ症候群」に悩まされることも少なくありません。ロシアで生まれ、イギリスで英語と造形学を学んだ彫刻家のザッキンも、渡仏直後は孤独を深め、自分は存在していないも同然のようだったと振り返っています。
しかしそこで自分らしさを曲げることなく、居場所を求めた人がカフェに行ったわけです。行けば行ったで、自分と似たような境遇で、しかも知的・芸術的な感度の高い仲間が多くいたわけですから、頻繁に足が向かうようになるのは当然のことと思います。つまり彼らは革新者としての自分を貫いたからこそ、 “カフェに通わざるを得なかった”ということです。
また、18~20世紀初頭くらいまでのパリはインフラや住環境が整備されておらず、トイレや電話、暖房のないアパートが珍しくなかったため、そうした機能を求めてカフェに通ったという面もあるでしょう。お茶だけでなくお酒も提供し、朝から晩まで営業する店も多くありました。リソースの幅の広さが人を集めたという意味では、今の都市開発でいわれるミクストユース(mixed-use/複合利用)の先駆けといえるかもしれません。
(トップ写真提供:飯田氏)

飯田氏のウェブサイト。カフェの社会的役割、パリのカフェの歴史や特徴の他、イタリアや日本、イギリスのカフェ文化なども含めて、豊富な情報が掲載されている。
https://www.la-terrasse-de-cafe.com/

飯田氏の著書『カフェから時代は創られる』(2008年いなほ書房より刊行、2020年クルミド出版より新版刊行)。後世に名を残す「天才」たちがどのようにカフェに集い、文化や時代をつくっていったか、自伝的記録の分析や関係者への取材を交えて丹念にひも解いていく。

飯田氏。取材はオンラインで行った。
“作品”でなく“存在”を肯定され
異端的な志向を伸ばすことができた
才能ある人々がカフェに集ったもう1つの要素として見逃せないのが、カフェの主人の存在です。
社会からつま弾きにされた人は委縮してしまいがちです。自分に自信が持てず、能力も思うように発揮できなくなってしまう。そこで必要なのが、どんな人でも一人の人間として認め、受け入れてくれる人の存在です。
客の地位、国籍、お金があるかどうかといったことを抜きにして、一人のお客としてもてなしてくれる。それはホスピタリティでもあり、商売繁盛の秘訣* でもあったでしょう。
1920年代には、ぼろぼろの服を着て、エスプレッソ1杯でずっと粘る貧乏な芸術家がたくさんいました。そんな彼らを邪険にすることなく、他の客と同じように受け入れるカフェがあったからこそ、芸術家たちは自分を見失うことなく、信じる道に突き進むことができた。それが結果としてブレークスルーにつながったのではないでしょうか。
カフェの主人は“作品”を認めたわけではないのです。むしろ、客がものした絵画や書籍には関心がなかったというエピソードが多く残っています。あくまで“存在”を認めたことがキーだと思いますね。
当時の価値観にそぐわない、新しい発想を持っていたからこそ、芸術家たちは社会に馴染めなかったわけですが、「あなたはあなたのままでいいんだよ」「何をやっているか分からないけど頑張れよ」と存在を丸ごと肯定し応援してもらうことで、彼らが信じる道へと進むことができた。それがイノベーションを育むことにつながったのだと思います。
偶発的な出来事がインスピレーションを刺激
もう1つ、人々がカフェに集った理由として指摘できるのは、そこが偶発性に満ちた場であったということです。
カフェは街なかの空間ですから、いろいろな人がやってきます。お客にはお金持ちもいれば貧乏人もいる。娼婦もいれば官吏もいる。政治的議論や哲学的思索もあれば、恋愛や失恋もあります。みんなの生身の姿、生の感情に触れることが芸術家の想像力をかきたて、インスピレーションを刺激したこともあったはずです。
また、パリのカフェでは予期しないこと、突拍子もないことが毎日のように起こっていました。議論が盛り上がるあまり乱闘騒ぎに発展することは日常茶飯事で、中には耳を切るなど傷害事件に発展することもありました。
価値観の揺らぎを経験し、自分の殻を破った
日本からパリに渡り独自の画風を確立した藤田嗣治は、モンパルナスのカフェに集う人たちを「万国人種展の五十ヶ国余りの人種から成り立って珍しき国の人々で、名前さえ初めて聞いた様な国の人達」と描写し、「されば奇想天外の考えも生まれて来るのは当然である」と述べています。「奇想天外の考え」とは、斬新な発想やイノベーションに通じるでしょう。
世界中から価値観の違う人々が集まり、思いもしない出来事に直面するという状況に身を置いていると、自分の常識がちっぽけに見えてくるものです。そうして藤田は「日本で覚えたものを、スッカリ洗い落としてしまったのだ。それから初めて自分の仕事にかかった」「何もとらわれない、自分の派を開くようでなければ駄目だ」という境地に至るのです。
藤田に限らず多くの人々は、予期せぬ人やコトとの出会いを通じて、価値観の揺らぎを経験しました。そうして今まで大事に抱えてきた“常識”は一体何だったのかと、自分の殻を破っていった。内にこもることに何の意味があるのかいう気づきを得て、そこから新たな表現、新たな価値を紡いでいったということだと思います。
パリのカフェテラスを文化遺産に登録する動きも
19世紀前半のパリのカフェは創造性やイノベーションを育む場であったわけですが、翻って現在はというと、残念ながらそこまでの熱狂はありません。
今はそれなりに住環境も整いましたし、オンラインでも交流できますから、それほど深い孤独に陥ることは少ないでしょう。ネスプレッソを持つ家庭が増えるなど、自宅でおいしいコーヒーも味わえるようになりました。そういう状況にコロナ禍が加わったことで、カフェに行くことのハードルが上がっているのが現状です。
とはいうものの、やはりカフェでお茶をすること、テラス席でくつろぐことがかけがえのない時間であることには変わりありません。コロナでカフェに行けなくなって、そうした時間のありがたみを多くの人が実感しています。
パリのカフェテラスをユネスコの文化遺産に登録しようという動きもあります**。需要の落ち込みは一時的なもので、しばらくするとまた賑わいが戻ってくるかもしれません。
WEB限定コンテンツ
(2021.1.13 オンラインにて取材)
text: Yoshie Kaneko
* デール・カーネギーは著書『人を動かす』の中で、ビジネスの成功に一番大事なことは、人を重要な人間として扱うことだと指摘している。「成功するカフェはどこもこの姿勢が徹底しています」(飯田氏)。
飯田氏が登壇するオンライントークイベントが紀伊國屋書店で開催される。「なぜ、パリのカフェが文化創造の場となったのか~『カフェから時代は創られる』著者・飯田美樹×クルミドコーヒー・影山知明オンライントークイベント~」2021年3月20日(土)17:30~19:00/Zoom(オンライン)にて。
詳細は紀伊國屋書店イベント案内ページへ。
https://store.kinokuniya.co.jp/event/
** 飯田氏によれば、パリでは地元のビストロ経営者らが中心となって、パリのビストロとテラスをユネスコの無形文化遺産に登録しようとする動きが2018年ごろからあるという。
ちなみに、ウィーンのカフェ文化は2011年にユネスコ無形文化遺産に登録された。2019年12月にはイタリア下院議会が「エスプレッソ」の無形文化遺産登録に向けて活動を開始すると表明している。

飯田美樹(いいだ・みき)
カフェ文化、パブリック・ライフ研究家。学生時代、環境活動の場づくりを通じて、社会が変わる場に関心を抱く。大学時代にパリ政治学院に留学し、現地のカフェに通うかたわら、カフェの研究を開始。帰国後、大学院に通い、「天才たちがカフェに集ったのではなく、カフェという場が天才を育てたのでは」という視点で研究をすすめ、『カフェから時代は創られる』(クルミド出版)を出版。現在は、街なかでリラックスした時を過ごせるインフォーマル・パブリック・ライフの重要性と、オープンカフェがいかに街の活性化に役立つかという視点で2冊目の本を執筆中。かつてのカフェのように世界の先端の知に出会い、議論し、つながれる場をつくろうと、オンラインで”World News Café”を主催している。Paris-Bistro.com日本版代表。東京大学情報学環 特任助教。(写真提供:飯田氏)
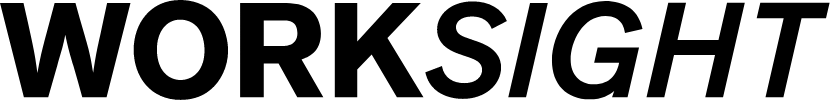
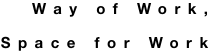
![働くしくみと空間をつくるマガジン[ワークサイト]](/images/common/ttl-catch_copy-002.png)







FacebookでWORKSIGHTを購読
TwitterでWORKSIGHTをフォロー
RSSを購読する