Innovator
May. 22, 2017

人類の惰性で起こる課題に立ち向かうのがデザインの役割
対話と観察を通してそもそもの課題点を発見する
[宇田川裕喜]株式会社バウム 代表取締役、クリエイティブディレクター
バウムの社名の由来は「場生む」です。
食べる、働く、学ぶ、遊ぶ、住む……僕らは日々さまざまな体験をしています。生きるということは多様な体験をし続けることであり、その体験を通して他の人とコミュニケートしていくことです。企業が行政が社会をアップデートしていく中で、どんな体験をつくって、人とどう関係をつくっていきたいかを探り、そのために必要な場をつくるのが僕らの仕事です。
その場は物理的なスペースであることもあれば、ウェブや広告の場合もあります。いずれにしても人と人、モノと人、街と人、企業と人といったコミュニケーションの場を生むことで、いい未来への変化をつくりたいと考えています。
行動範囲を広げ冒険を促した、まちづくりプロジェクト
場の可能性の広がりに気づいたきっかけは、小学生時代に参加した地域のまちづくりプロジェクトにあります。
僕は東京・杉並で生まれ育ったんですが、杉並区は体験を通して地域を知ろうという試みを1980年代から進めていました。例えば「知る区(しるく)ロード」* という区全域を周遊する散策路は、公園や名所旧跡、主だった施設などを効率よく巡ることができるというものです。夏休みの「まわれ児童館!」というスタンプラリーでは、オリジナルグッズほしさに区内数十か所の児童館を自転車で全てまわったことを覚えています。
生まれ育ったエリアだから目新しいものはもうないと思っていたけれども、すみずみまで回ってみると意外な発見があるとわかった。当時僕は小学3〜4年生で、行動範囲はせいぜい自宅から半径2キロくらいでしょうかね。でもこの企画で区内全域、7キロくらいに広がりました。小学生にとっては冒険ですよ。自治体の住民啓発というといわゆる学習的な内容になりがちですが、これはゲーミフィケーションもとり入れた全国的にも先進的な取り組みだったと思います。
建物を新しく作ったとかお店を開いたといったことではなく、コミュニケーションやアイデアの力で「場」を生んだ。その場が僕の視野を大きく開き、世の中とのつながりを強くし、世界のあり方を変えてくれたわけです。自分もこういう仕事がしたいと思いました。企画した区役所のまちづくり推進課は、しばらく僕の憧れの就職先でした(笑)。
社会の共感を呼び、良質な変化へとつながる場を具現化する
バウムでも、企業活動や社会の課題を解決する際に体験の連続による関係の変化に着目しています。何か変化を起こしたいとき、新しいことをはじめるとき、知ってもらいたい人たちに知ってもらうことが必要になります。単なるプロモーションではなく、社会の共感を呼び、さらに変化につながるものをつくる。それがクライアント企業と社会にとって価値ある「場」になると思います。
それをどうデザインに具現化するか。アウトプットの形は案件に合わせて自由に変えるのですが、川上でコンセプトを固める段階ではそもそもの課題点を見つけることに重点を置いています。
例えば、企業のオフィスデザインを構築した案件では、仕事をする上でどんな課題があるか、これからどんな働き方をしたいかという点の前に、この場をつくることで誰と誰の関係をどう変化させたいかを深く掘り下げていきました。建築設計チームは要件に基づいて具体的な形に落とす前提から進む一方で、僕らは体験づくりと関係づくりに重きを置いた話し合いを重ねていったんです。すると、日本人社員と外国人クライアントとのコミュニケーションをもっとスムーズにしたいという課題が浮上してきました。
新しいものを作るには外部の視点が有効
外国人とのコミュニケーションにおける文化的な違いは、建築やデザインでは解決できないようにみえます。だから、与件書にもはいっていません。そういう本質的な課題は常識を疑ってみないと見えてきません。話し合うことってすごく大事で、クライアントの話にじっくり耳を傾け、こちらの思いも丁寧に伝えていきます。
そういう隠れた本質を探すには外部の視点は有効で、そこにデザイン的に考える専門職の意義があるし、こうありたいという未来の場をあれこれとイメージすることで初めて見えてくるものもある。そのうえで社会の方を向いて、クライアントの視野を広げることができると面白いです。
プロジェクトチームのメンバーともよく話します。特に他の会社との合同プロジェクトでは、専門とする業界がそれぞれ違っていたりしますからね。個別の業界について自分で調べて研究するのも限界があるので、その分野に詳しい人と飲みに行って、じっくり話を聞くんです。クライアントとのコミュニケーションを深めるためにも、人と話す時間をいい形で作ることは意識しています。

株式会社バウム(BAUM)では、コンセプトデザイン/エクスペリエンスデザイン、広告キャンペーンの企画制作、店舗等の企画、コピーライティング/ネーミング、紙媒体/WEB媒体制作などの事業を展開。米国オレゴン州ポートランドの企業との共同プロジェクトも進めている。設立は2010年。
http://ba-um.jp/
* 防災、まちづくりの意識啓発、まちの施設や資源を知る、高齢化社会の体力づくりと余暇活用、杉並区という意識づくりという5つのコンセプトを軸に、杉並区が1988年に整備した散策路。

「人よりいいモノ」から、
「人といい時間を過ごしたい」時代へ
そもそもの課題を抽出するとき、徹底的に話し合うことのほかにもう1つ大事にしているのが「観察」です。
ある百貨店のフロアのリニューアル計画を依頼されたときのこと。その百貨店は安定した営業力はあるものの、それゆえに現場の改善意識が薄れてしまっているということでした。そこで社内の意識改革を促しつつ、次世代の買い物のあり方を示すような、新しい人の流れを作りたいというリクエストだったんです。
そこで飲食分野に強いプロデュース会社とチームを組み、あれこれ考えながらコンセプト立案に取り組んだんですが、このとき客層の違う郊外型ショッピングモールを巡ってお客さんや店員を観察して回ったんです。5年後、10年後の百貨店のお客さんになるはずですから。
あちこちをつぶさに見てわかったのは、ステレオタイプな印象ほど楽しそうな感じがしないということ。疲労感とか孤独感も結構あって、お買い物って意外と楽しいものではないのかもしれないと気づきました。では百貨店でどういう時間を過ごせればいいか、さらにクライアント百貨店ならではの個性は何かを、飲食チームも交えて考えていったんです。
クライアントの強みを紐解き、新たな人の流れをつくる
その結果、お客さんは新しいことに興味があるけど臆病な部分がある。また、クライアントのブランドの信頼は厚い。この組み合わせに大きなヒントがあるはずという結論に至りました。包装紙を見ただけで「いいもの」と思ってもらえる。買い物に行くときも身だしなみを整えて、ちょっとおしゃれしていく。そういう非日常感を提供できる場所なんですね。このブランド力があれば、多少とんがったものもお客さんに受け入れてもらえると踏みました。
アウトドアやデジタルのこと、何か新しいことを始めるときには、同じような仲間がほしいものです。たとえば山登りなんてひとりではなかなか始められません。そこで、仲間もできる売り場はどうかと考えました。
最終的に出来上がったのが、大きなポップアップストアとワークショップスペースを備えた店舗でした。開店時にはツリーハウスを体験・購入できるポップアップストアを設置しました。実物のツリーハウスを置いて、大きさを確かめたり手触りや香りを楽しんだりできるようにしました。販売価格は100~200万円もしますから、ひょっとすると売れないかもしれない、でも新しい人の流れを作ることはできるはずだと、どきどきしながら初日を迎えましたが、ありがたいことにお客さんの評判は上々で商品もいくつか売れたんです。
100万円の高級時計もいいですが、ツリーハウスを買って子や孫との時間を楽しむのもいい選択肢だと思ったんです。豪邸の庭にあってもチャーミングですし、北欧のサマーハウスのような使い方ができたら地方への人の流れも作れるし、とても豊かな過ごし方が生まれると考えました。これはその後、日本での小屋ブームの端緒になるような動きにもつながりました。
完成品が生む惰性に思考停止するのは人として自然な姿
この百貨店のプロジェクトでは、売り場を考えて運用する体制をつくりたいという隠れた意図もありました。催事場はいつしか外部業者の持ち回りの仕組みができていて、出来上がったら終わり、後はその枠の中でいかにお客さまに良さを伝えるかという組織文化を変えるということです。
場は「つくる」と「運用する」の両面の要素があります。つくって終わりでなく、お客様とのコミュニケーションの中で見せ方に工夫を加える運用の意識が必要です。そこで、このプロジェクトでは仕組みのデザインにも取り組みました。ポップアップスペースを外部に全面委託するのを禁止して、社内で考えてもらうようにしました。
ある形に仕上がったものを「もう完成したから手を入れる必要はない」と思考停止してしまうのはごく自然です。そして人は楽ちんな方に流れがちです。それが当たり前だし、自然な姿でもあるでしょう。そこで考えるように促すのは不自然なことですが、それが必要なんです。大きな変化を作っていくには、惰性に対してデザインでの解決に取り組んで、新陳代謝を促していかないといけない。
安定しているものを不安定にする、それがデザインの本質だと思うし、上からの指示だけで動くのではなく、そもそもを考えて個人それぞれが自分で考えることで本質的な解決を目指していくのがデザイン思考といえるでしょう。それを現場に浸透させるための取り組みでもあったということです。大規模な仕事ではなかったですが、この百貨店の変化のきっかけ作りにはなったのではないかと思いますし、100年以上続く場への挑戦は学びも多くありました。
WEB限定コンテンツ
(2017.3.8 渋谷区のバウムオフィスにて取材)
text: Yoshie Kaneko
photo: Kei Katagiri


セルフメイドのロゴや看板が飾られたバウムのオフィス。温かさの中にも洗練された空気が漂う。

宇田川裕喜(うだがわ・ゆうき)
東京都生まれ。大学時代は環境雑誌記者として企業取材をしながら世界各地を探訪。広告業界を経て、コミュニケーションの力で「場」を生み出すことで企業や社会の課題解決を図る株式会社バウムを2010年に設立。社会人向けの市民大学「丸の内朝大学」のプロデュースなどを手がける。2012年より米国ポートランド、2016年からデンマーク・コペンハーゲンでも活動を開始。現地での場づくりのほか、日本企業の現地展開もサポートしている。
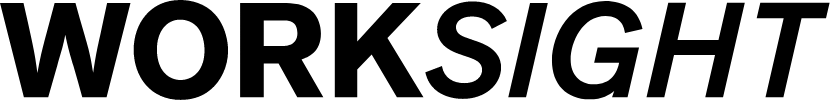
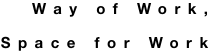
![働くしくみと空間をつくるマガジン[ワークサイト]](/images/common/ttl-catch_copy-002.png)



