Foresight
Sep. 22, 2014

日本企業は原点回帰で「知識機動力」を獲得せよ
知識創造を加速する実践知リーダーシップ
[野中郁次郎]一橋大学 名誉教授、米カリフォルニア大学バークレー校 経営大学院 ゼロックス知識学 特別名誉教授、早稲田大学 特命教授
世界の中で日本企業のプレゼンスが低下しています。これは30年前には考えられなかった状況です。
1980年代は日本企業の黄金期でした。円高の影響もあって海外進出が進み、世界で幅を利かせていた。アメリカで『ジャパン・アズ・ナンバーワン』(エズラ・ヴォーゲル)という本が出版されたことが象徴するように、日本企業はまさにグローバルビジネスを席巻していたわけです。
米国ではとりわけ日本的経営が評価され、研究の対象となりました。世界的大ヒットとなったビジネス書『エクセレント・カンパニー』(トム・ピーターズ、ロバート・ウォーターマン)では、IBM、GE、3M、プロクター・アンド・ギャンブル、デュポンといった米国企業が超優良とされましたが、著者たちはそうした企業には日本企業と通底するところがあるとも指摘しています。ビジョンを大切にする、その企業の価値を大切にするといった特徴のほか、中でも注目を集めたのがアクションバイアス(行動志向)です。
分析過多、計画過多、コンプライアンス過多の日本企業
当時のアメリカでは、MBA教育の普及につれて分析的アプローチが主流となっていました。これに対し、経営学者のH・ミンツバーグは、マネジメントは「アート(直観)」「クラフト(経験)」「サイエンス(分析)」の融合と説いたけれども、分析重視の傾向は止まりませんでした。分析を重視するということはサイエンスに大きな比重を置くということです。軍隊なら、Ready, Aim and Fire(用意、狙え、撃て)という順番ですね。
しかしアクションバイアスというのはそうではない。日本企業やエクセレント・カンパニーの特質は、分析以前にまず行動ありきだということです。Ready, Fire and Aimなんですよ(笑)。分析や理論化は行動の後についてくる。現実を直視して、とにかく行動を起こす企業こそが競争力を持ち、持続的に成長を遂げうるのだと、米国の研究者やコンサルタントは看破したんです。
『エクセレント・カンパニー』の後、企業競争力の源泉を基本理念に求める『ビジョナリー・カンパニー』(ジム・コリンズ他)が出版されましたが、これもビジョン、生き方の重要性を説いています。長く生き延びてきた企業を見ると、どうもやはりマネジメント・アズ・サイエンスでは企業は続かないということが分かってきたのです。
しかしながら、90年代以降、日本企業はこれと逆行する道を来てしまった。欧米流の分析的な経営手法に過剰適応し、本来の持ち味を失ってしまったわけです。分析過多(over-analysis)、計画過多(over-planning)、コンプライアンス過多(over-compliance)という現象が、今の日本企業から活力を奪っていると思います。
分析も計画もコンプライアンスも必要ではあるけれども、あまりにも緻密にルールを決めると身動きできなくなってしまいます。要はバランス感覚の問題です。欧米の企業はコンプライアンスを徹底的に研究して、アウトコースギリギリで勝負をしてくる。日本は考えすぎた挙句、直球をど真ん中に入れてしまう。それじゃ打たれるに決まっています。
サイエンスを重視しても、状況は絶えずダイナミックに動いていますので、分析から予測はできないんです。いまや、分析型の経営手法を編み出した欧米ですら、これを改めて、アートやクラフトも重視しています。しかし、日本は相変わらず分析に明け暮れて、自縄自縛でビジネスを硬直化させている。これが今の日本企業の停滞の根底にある問題だと思います。
実践知リーダーシップの6要件
日本企業が停滞を改善するには、変化のただ中において、個別具体の文脈でジャストライト(ちょうど)の判断ができるフロネシス* =「実践知」を企業の現場に醸成することが必要です。
実践知を備えたリーダーは、断片的な情報や知識に偏ることなく、ダイナミックな状況の本質を察知して、その時々の文脈に最善の判断・行動を起こすことができます。アート、クラフトとサイエンスを総合するわけです。そういうリーダーシップを「実践知リーダーシップ」と私は呼んでいます。具体的な要件は次の6つです。
(1)「善い」目的をつくる能力
(2)ありのままの現実を直観する能力
(3)人々が創発し合える場をタイムリーにつくる能力
(4)直観の本質を物語る能力(戦略立案能力)
(5)物語(戦略)を実現する政治力
(6)実践知を組織する能力
まずは、みんなが善いと思えるような共通善の価値基準に沿った目的を掲げること。これが実践知リーダーの一番の要件です。三井物産の長期業態ビジョンの「良い仕事」、伊那食品工業の社是「いい会社をつくりましょう」、トヨタ自動車の唱える「もっといいクルマづくり」などは、このいい例でしょう。
2番目は、ありのままの現実を直視して、その背後にある本質を直観的に見抜くこと。現実を直観するということは、現場に出る、ということです。机上で分析しているだけではだめで、現場のただ中に身を置いて五感を駆使して洞察力を働かせるわけです。
3番目は場づくりですね。プロジェクトチームの立ち上げなどは典型的な例です。適材適所の人材を集めて、それぞれの経験を持ち寄りながら、自分たちの思いをコンセプトに編み上げていく。そこでは人間的な魅力も問われます。
4番目はそのコンセプトを物語にする。戦略は現状をどのように変えていくかという筋書きを語るある種の物語りです。チームメンバーが納得し、モチベートされるような形に理論化、モデル化するわけです。
5番目はそれをやり抜く。イノベーションを実現するには抵抗勢力を抑え味方を増やす説得力も必要です。それは政治プロセスと言っても過言ではないので、したたかさとしつこさをもってやり抜かないといけません。
そして6番目は、組織のメンバー全員が実践知のリーダーシップの能力を持ち発揮できるようになること。松下幸之助氏の言う「衆知経営」はまさにこれです。リーダーの役割は、メンバー全員が知恵を出し合える場を整え、みんなの知恵を経営や事業に活かす仕組みをつくることです。
暗黙知と形式知を相互変換するSECIスパイラル
重要なのは、この6要件がスパイラルアップしていくことです。組織メンバー全員に実践知のリーダーシップが備わることで、組織として「善い」目的をつくる能力は確実に高まります。メンバー間の相互作用を通してスパイラルさせることで実践知に磨きをかけるわけです。
同時に、この6要件を実現するということは、実践知を表出し、みんなで共有する機会を設けることでもあります。個人の内面には経験や勘に基づいた、まだ言語化されていない知識、すなわち暗黙知があります。これに対して、文書化・マニュアル化された知識を形式知と言いますが、実践知リーダーシップが機能すると、暗黙知と形式知の相互変換のスパイラルも促進されるのです。
このスパイラルは、「共同化(Socialize)」「表出化(Externalize)」「結合化(Combine)」「内面化(Internalize)」の頭文字からSECI(セキ)スパイラルと呼んでいます(下図参照)。

一橋大学大学院国際企業戦略研究科では、グローバルに活躍するスペシャリストを育成。野中郁次郎氏が提唱する知識創造経営を基盤とする「国際経営戦略(昼間・英語、MBA・DBA)」のほか、「金融戦略・経営財務(夜間・日本語、MBA・DBA)」「経営法務(夜間・日本語、修士・博士)」という3つのコースで構成されている。
http://www.ics.hit-u.ac.jp/
* フロネシス
アリストテレスが『二コマコス倫理学』で提唱した知を分類する概念のひとつで、「賢慮」「実践理性」とも翻訳される。野中氏は、倫理の思慮分別をもって、その都度の文脈で最善の判断・行為ができる実践的な知力と定義している。
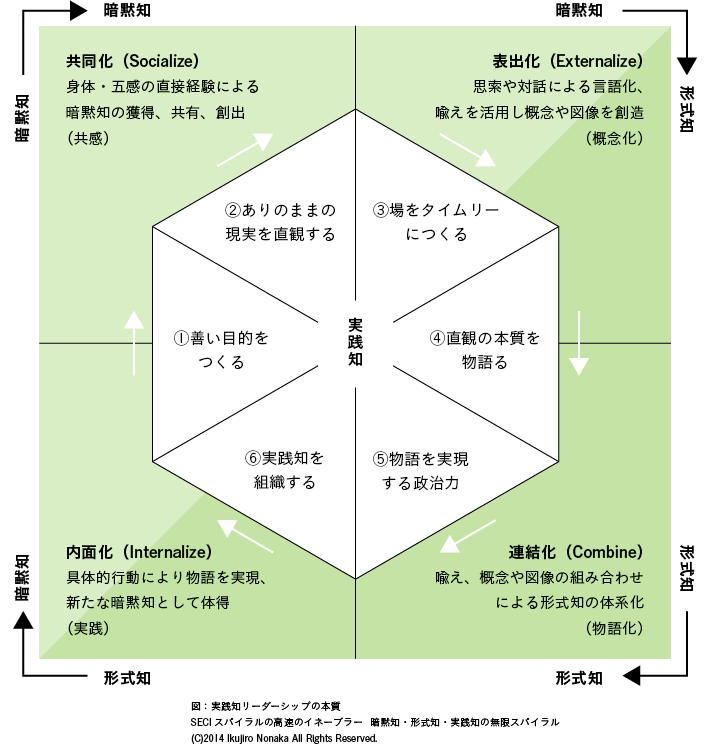
日本企業にはリスクを取る積極精神と
物事を進めるスピードが欠けている
SECIスパイラルがPDCAサイクルに似ていると感じる方もいるでしょうが、PDCAサイクルは初めに計画ありきの効率追求モデルで、サイクルを回しても計画以上のことは出てきません。対してSECIスパイラルは、まず経験ありきです。深い暗黙知から付加価値となる知識を創造するイノベーションモデルで、スパイラルを回すことによって常に新たな知識が創造されます。したがって、この2つは根本的に違います。
初めに申し上げたように、かつて元気だったころの日本企業と、成熟を続ける米国企業の共通点として、客観的な分析ではなく、主観的な経験に立脚していることが挙げられます。だからと言って、分析が全く不要かと言えばそうではありません。競争力を高めるには経験と分析の相互作用のスパイラルを回転させていくことが重要です。それもスピーディに機動的に回さないといけない。高速回転させて、個人の暗黙知を形式知に転換して組織で共有し、より高次の知識を創造するのです。すると何が起きるかといえば、ビジネスの現場に「知識機動力」がもたらされます。実践知リーダーの究極の目的はここにあります。
知識機動力とは、トップが描くビジョンに向かって、ミドルを中心にした現場の人材が組織の各所に自律分散するリーダーとなり、付加価値の源泉である知識を高速かつテンポよく創造する力のことです。上位の企業戦略レベルから下位の日常の業務レベルまで一貫して知識機動力が実践されることによって、柔軟な構想力と行動力を組織のどのレベルにおいても発揮できるフラクタル型の組織となります。フラクタル型の組織は、すべてのレベルで組織全体と同じ決断ができるので、スピーディに判断力と行動力を発揮できるのです。
今の日本企業には、リスクを取りに行く積極果敢の精神と物事を進めるスピードが欠けています。これを補うのが知識機動力です。知識機動力の獲得はレジリエンスの維持・強化に直結するものでもあります。
ソフト開発は「リレー」から「サシミ」、そして「スクラム」へ
このスパイラルをビジネスの現場で効果的に回すには、組織メンバーが緊密につながっている必要があります。特にプロジェクトではこれが必須です。
製品開発を例に考えてみましょう。「リレー」形式の開発は多くの現場で見られる体制です。メンバーは割り当てられた機能のプログラミングに注力し、全体として出来上がったものを1つのシステムに統合していきますが、メンバー間のつながりはほとんどありません。1980年代の欧米では、このスタイルが主流でした。
ところが、我々が研究した元気だったころの日本企業では、メンバーの担当領域が部分的にオーバーラップしていました。これを刺身の盛り付けになぞらえて「サシミ」と呼んでいます。
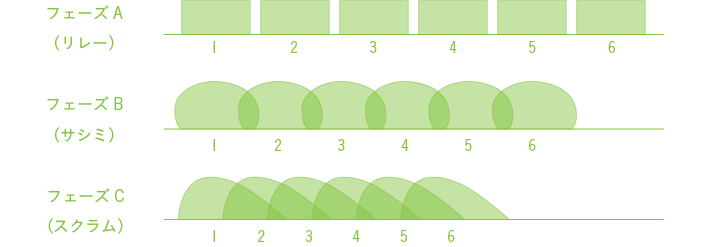
さらに、もっと結びつきが強まると、ラグビーのようにメンバーががっちりと組み合わさる「スクラム」になります。こういう体制ができたプロジェクトチームは機動力が高まり結果を出すスピードが速くなります。機能単位で階層や組織が分割されないので、チームメンバーの「共同化」「表出化」の質が高まり、それが技術的な知識の「連結化」を推し進め、より良い製品に結実し、「内面化」によって結果として技術的な専門知識をチームや組織の資産へと変換することができます。
このスクラムをソフトウエアの開発に取り入れたのが、アジャイル・スクラム方式の開発プロセスです。例えば、仕様策定、設計、プログラミングなどフェーズや機能別に完結したウォーターフォール型の開発では、プログラミングの現場で判明した仕様の不備をリレーのひとつずつの段階をさかのぼって修正しなければならないので、時間もかかるし非常に難しい。けれどもアジャイル・スクラム開発では、毎朝のスクラム・ミーティングの場や、ペア・プログラミングの場などで、すぐにフィードバックができます。顧客とも常にミーティングの場を設けているので、より機動的でレジリエントでもあります。
1980年代の日本企業ではスクラム型の開発体制が多く見られましたが、むしろ今はリレー形式で分業化してしまっている。一方、アメリカのソフトウエア開発ではスクラム形式をベースにした「アジャイル・スクラム」という開発技法が主流になっており、ほかの業種にも影響が及んでいます。
毎日、同じ時間、同じ場所の会議でメンバーの結束を強める
アジャイル・スクラムで重要なのは、毎日、同じ場所、同じ時間、同じ参加者で会議を行うスクラム・ミーティングです。この会議を通じてメンバー間の親密さが高まります。結果として、知識を共有する習慣が作られ、日々の開発プロセスの改善が促進されるわけです。まさに知識創造です。
他にも顔を合わせてコミュニケーションを取ることが重視されています。その意味では会議だけでなく、例えば開発用コンピュータをベテランエンジニアと新人エンジニアでペアで使うのも有効でしょう。経験や技術力に差がある人同士でペア・プログラミングを行うと、新人は先輩のソフトの使い方やコードの組み方を見て学びます。自然と上位の人にレベルを合わせることになるので、成長のスピードと質が飛躍的に高まるわけです。言ってみれば現代の徒弟制です。
さらに、開発では「タスクかんばん」を使って作業内容の見える化を行います。良いやり方はキープし、改善点はフィードバックし、上手くいっていないところは試行錯誤しながら、互いに知識と知恵の共有を図るのです。これはKPT(Keep/Problem/Try)フィードバックと呼ばれるものですが、要するにSECIモデルを高速回転しているわけです。
このように、メンバー同士が、あ・うんの呼吸で分かり合うような一体感のある緊密さで結び付くところまで行くとSECIモデルは高速に回転し、知識機動力も強力になります。スクラム・ミーティングも徒弟制もタスクかんばんも、もともとは日本企業が行っていたものです。これらをアメリカの企業がリファインしてアジャイル・スクラムという型に仕上げたのです。したがって日本企業にもこのDNAは残っているはずです。今こそ日本企業は原点回帰で知識機動力を獲得すべきです。
WEB限定コンテンツ
(2014.6.4 千代田区の一橋大学にて取材)
図:連続的(A)vs. 重複的(BおよびC)開発フェーズ
(出所:Takeuchi, H. & I, Nonaka. (1986). The new new product development, Harvard Business Review January-February, 1986.)
アジャイルとは「俊敏な」「素早い」という意味。

野中郁次郎(のなか・いくじろう)
一橋大学 名誉教授、米カリフォルニア大学バークレー校 経営大学院 ゼロックス知識学 特別名誉教授、早稲田大学 特命教授。1935年生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業後、富士電機製造株式会社(現・富士電機)を経て、カルフォルニア大学バークレー校で博士号を取得。南山大学、防衛大学校、一橋大学各教授、富士通株式会社取締役、エーザイ株式会社取締役などを歴任。主な著書に『失敗の本質』(中央公論新社)、『イノベーションの本質』(日経BP社)、『流れを経営する——持続的イノベーション企業の動態理論』(東洋経済新報社)など多数。
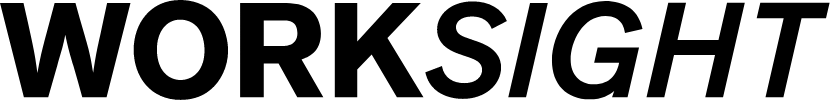
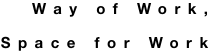
![働くしくみと空間をつくるマガジン[ワークサイト]](/images/common/ttl-catch_copy-002.png)



